古代紫 [西洋史・オリエント史]
古代紫
Tyrian purple

“古代紫”という言葉の響きって、すっご~くいいと思いませんか?
わたしはとても好きです。
あなたはいかがですか?
古代紫ってどのような色だか、あなたにもなんとなく分かっているでしょう?
でも、実際どのような色のことを“古代紫”と呼ぶのか?。。。考えてみた事がありますか?
この記事では、そのことについて考えてみようと思います。
岩波の理化学辞典には、 Tyrian Purple は「古代紫」の名称で取り上げられています。
この項には次のように書かれています。
 【古代紫】
【古代紫】地中海産の貝
purpura、Murex、Thais 属の
鰓下腺(サイカセン)から分泌される黄色液で、
主な色素成分は、
6.6’-ジブロモインディゴ C16 H8 O2 N2 Br2。
これで繊維を染めて空気にさらすと、
紫に近い深紅色に変わる。
ギリシャ・ローマ時代における
貴重な紫色素で高価であった。
ところで私が日常使っている三省堂の国語辞典には次のように出ています。

【古代紫】
多少灰色がかった紫。
江戸紫よりも黒味を帯びている。
私の頭の中では「古代紫」というのはTyrian purpleのことなんですが、国語辞典の定義にある「古代紫」とは全く違っているようですよね。
Tyrian purpleと言う色は理化学辞典で説明されているように「紫に近い深紅色」なんですね。
国語辞典で定義されているような「多少灰色がかった紫。江戸紫よりも黒味を帯びている」色ではありません。

では、Tyrian purpleとはどのような色をしているのかと調べたら、右の絵に書かれている人物が身にまとっている帽子と上着の色がその色なのです。古代紫とも江戸紫とも違い、かなり赤みを帯びています。
古代紫には人によってかなりの受け止め方に違いがあるようです。
むしろ「貝紫」と言ったほうが的確かもしれません。
貝紫とは磯に住むイボニシやレイシ、アカニシ、センジュガイといったアクキガイ(悪鬼貝)科の巻貝(murex)から取れる染料のことです。
この貝が持つ鰓下腺(通称パープル腺)から分泌される乳白色~淡黄色の液は、太陽の光にあたると酸化されて紫色に変化する性質があります。
この分泌液は6.6ジブロムインディゴと呼ばれる色素の1種が還元された状態で貯蔵されているもので、神経を麻痺させる作用があるため、他の魚貝類を攻撃する武器になると共に産卵期には卵殻の中に注入して、卵が他の生物に食われないようにする役目も果たしています。
アクキガイ科の貝の中には食用になるものもあり、大昔から海辺の人々によって採捕されて来ましたが、殻を割って料理する際、内臓が手や衣服に付着して紫色に変化するのを見て、染色に利用することを思いついたのでしょう。
この貝から取れる染料に基づいた染色法は地中海沿岸の古代フェニキアで行われ、それがギリシャ・ローマ時代に受け継がれていったものです。
これで染めた衣服を着られるのは王候貴族に限られていました。
歴史書によると、貝紫は1gの染料を取るために二千個もの貝を必要としたとあります。
ちょっとオーバーじゃないかと思うのですが、とにかく希少価値であったことには違いないようです。
そのようなわけで極めて高価な色として珍重されました。
ちなみに1万個の貝から1gと書いてあるウェブページがありました。
二千個でもオーバーだと思ったのですが、1万個はさらにオーバーじゃないかと思いますね。
でも、それ程わずかしか取れないということは、このような記述から確かなようです。
Tyrian purpleとは“Tyre(ティルス)で貝から取れた紫”ということです。
このTyreというのは古代のフェニキアの都市です。
現在は es-Sur と呼ばれるレバノンにある小さな村です。

このフェニキア人は、紀元前15世紀頃から紀元前8世紀頃にティルス、シドン、ビュブロスなどの都市国家を形成して海上交易に乗り出し、のちにはカルタゴなどの海外植民地を建設して地中海沿岸の広い地域に渡って活躍しました。
フェニキア人は系統的には様々な民族と混ざって形成された民族です。
彼らはアフロ・アジア語族セム語派に属するフェニキア語を話し、言語的に見ればカナン人の系統に属する民族です。
彼らが自分たちの言葉を書き表すために発明したフェニキア文字は、ギリシャ文字・アラム文字・アラビア文字・ヘブライ文字など、ヨーロッパ・西アジアの多くの言語で用いられる文字の起源になりました。
もちろん、英語のアルファベットもこの系統です。
貝紫はこの古代フェニキア人が最初に染料として用いたことになっていますが、歴史研究者の中には、その起源はもっと古くクレタ文明(ミノス文明とも呼ばれます)でも使われていたとする人たちも居ます。
レウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島が、上の地図で示したようにクレタ本島の南東にありますが、この小島には初期のクレタ文明(紀元前3000-2200年)の頃に貝紫が取引されていたという記録が残っています。紀元4世紀までは人が住んでいましたが、現在は無人島です。
個人的には私は貝紫の起源はクレタ文明だと思いますね。
なぜなら、この文明は男も女も身だしなみに、ことのほか気を使ったのです。
考古学者のアーサー・エヴァンズはクノッソスで発掘調査した時に次に示すフレスコ画を見つけました。
これを見た彼は“可愛いパリジェンヌ”と言って驚いたという話が伝わっていますが、確かにナウい感じがしませんか?

“Ladies in Blue” fresco from Knossos, 16th century BC.
この3人のクレタ女性はお祭りでなにやら愉快に話しをしています。
当時上流社会で流行していた胸を見せる短い胴着(bolero)を身に着けています。
当時も細いウエストが好まれたそうです。この胴着の肩当を見てください。
これは貝紫で染めてあると思いませんか?ちょっと色が茶色っぽく変色していますが、これが描かれた時にはもっと赤みを帯びていたのではないでしょうか?

ヘアスタイルといい現代風なスカートといいセックスアピールする胴着といい、もしクレタ島の“パリジェンヌ”と19世紀のパリジェンヌが次に示すように町の通りを歩いていたら、19世紀の女性はダサいと思われてしまうのではないでしょうか?
我々の眼にはフープ・スカートは明らかに時代遅れと映りますよね。


“どちらの女性と喫茶店に入って話がしたいですか?”と問われれば、私はおそらくクレタ島の女性に声をかけるでしょう。
バルキーなスカートをはいた女性は、やはりダサいですよ。クレタ島の女性の方がモダンな感じがしませんか?19世紀の女性のように、こんな幅広のスカートをはいて喫茶店に入ったら、周りの人が迷惑するでしょうね。(笑)
19世紀の女性と比較するのでは、時代が違いすぎるので、同じ時代のエジプトの女性と比べてみたいと思います。
次の絵の中の女性たちは今から3500年から3000年前の服装をしています。
上のクレタ島の“パリジェンヌ”とほぼ同じ時代です。

一目見ただけでも、エジプトの女性の方がシンプルですよね。というか、言葉は悪いですが“土人スタイル”ですよね。
パリジェンヌよりも原始的な感じがします。我々の眼には、どう見てもクレタ島の女性の方が現代的な印象を与えます。
そう思いませんか?
いづれにしても、クレタ文明では5000年も前から貝紫が使われていたんです。
その貝紫を抽出していたのがレウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島だったわけです。
恐らく、この島からフェニキア商人によって抽出技術がティルスに伝わったのでしょう。
ところで、日本にも古代地中海から伝わったものがあります。
それは古代に中国の絹織物がヨーロッパへと運ばれてた道、シルクロードを通じて運ばれてきました。
奈良の正倉院に収められている楽器を彩る紫の色は古代の日本でも最も高貴な色とされていました。
でも、それは日本独自の考えで紫を選んだわけではありません。
紫を最高級の色とする考えは、地中海でとれる貝紫という染料から始まっているのです。
ところが、貝で染める紫の染料は弥生時代の日本でも使われていたのです。
佐賀県の吉野ヶ里遺跡は弥生時代先期から中期(B.C.3世紀~A.D.1世紀)の古代人の遺跡です。
吉野ヶ里遺跡では弥生中期頃の甕棺墓が多数発掘されています。
その甕棺に葬られていた人骨に付着している織物を分析した結果が報告されています。
その報告によると、布は絹織物で蚕の種類は違っているようですが、日本国内の蚕から得られたものです。またその絹織物の一部に貝紫で染められたと見られるものが残されているのです。
当時、絹織物を身につけることのできた人物は、集落の中でも高い身分の人であったと考えられます。
貝紫染めの織物を身につけることのできた人物は極く限られた人であったでしょう。
ここで問題です。貝紫染めは地中海沿岸だけで行われていたと考えている人が多いようです。
吉野ヶ里遺跡で国産の絹が貝紫染めされていたということは意外な感じがします。
日本でも弥生時代にすでに貝紫染めが行われていたという事実をどのように解釈すればよいのか?
極めて難しい染色がなぜ地中海と、遠く離れた有明海で行われていたのか?
現在のように通信手段の発達した世界ならば、情報はあっと云う間に地球の端から端まで伝えられます。
しかし、今から2000年以上も昔に地球の表と裏で、なぜ同じような染色が行われていたのか?
どうしてだと思いますか?
興味ありませんか?
もし関心があったらぜひ次のリンクをクリックして読んでみてくださいね。
意外な事実を発見できますよ!
では、また近いうちに、お会いしましょうね。
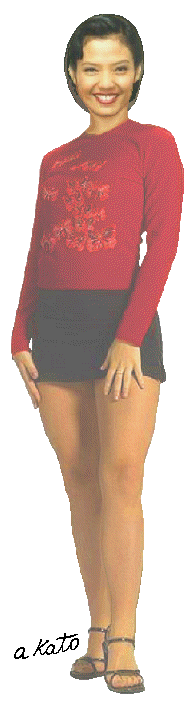
いにしえの美女 [西洋史・オリエント史]
いにしえの美女

Birth of Aphrodite by Alaxandre Cabanel (painted in 1863)
(この絵は一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「また、このアフロディテの絵ですか?ロブソンさんはよほどこの絵が気に入っているようですね」
「分かりますか?」
「これだけ何度も見せられたら分かりますよ」
「ジューンさんが何度と言うほど貼り付けていませんよ。これが3度目です」
「3度も見せられたら、充分すぎるほどですよ」
「ジューンさんは、こういう絵が嫌いですか?」
「嫌いじゃないですけれど、こうたびたび見せられると見飽きますよ」
「見飽きますか?」
「もちろんですよ」
「僕は何度見ても見飽きませんよ」
「そのうち見飽きますよ。それで、この絵とアメニアさんは、どのような関係があるわけですか?」
「実は、この絵からインスピレーションを受けてアメニアさんを描いたんですよ。それが次のイラストです」
(上のイラストは一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「また、この絵ですか」
「この絵も見飽きましたか?」
「見飽きたわけではないですけれど、ちょっとどぎついですよ」
「こういう絵は嫌いですか?」
「ロブソンさん、もう、絵のことはいいですから、このアメニアさんのことをお聞かせください」
「分かりました。前にも書いたことだけれど、この“ラピスラズリと美女アメニア”というのは僕が英語で書いた“Erotica Odyssey”の第1章なんですよ」
「ええ、聞きました」
「英語では“Lapis lazuli and Courtesan”と言う題名が付いています」
「と言うことは、日本語の題名ではCourtesanを“美女アメニア”としたわけですね」
「そうです」
「どうしてですか?」
「Courtesanのうまい訳がどうしても浮かんでこないんですよ」
「高級娼婦ではないのですか?」
「うん、確かに、そういう風に訳すのが一般的だと思う。たまたま、僕が良く使う“英辞郎”で調べてみたら、なんと“売春婦”と出ているんですよ。とてもじゃないけれど『ラピスラズリと売春婦アメニア』とはできませんよ」
「だから、『ラピスラズリと高級娼婦アメニア』にすれがいいじゃないですか?」
「でもね、僕には高級娼婦という言葉がどうしても馴染めないんですよ」
「どうしてですか?」
 「ジューンさんはoxymoronという言葉を知っているでしょう?」
「ジューンさんはoxymoronという言葉を知っているでしょう?」
「ええ、知ってますよ。日本語で言うと。。。」
「英和辞典には撞着語法って書いてあるよ。でも、これじゃあ、何のことだか分からないよね。例えばcruel kindnessという語句がある。 cruelは残酷なとか無慈悲なという意味だから、親切という意味のkindnessとは全く正反対の意味だよね」
「そうです」
「だから、普通の使い方では、このような用法は可笑しいわけですよ。普通なら、sweet kindnessと言うような組み合わせですよ。甘いやさしさ。これなら、問題がない。でも、時にはcruel kindnessがぴったりするような状況がある」
「例えば?」
「そうだね。。。例えば、子供が皿を5,6枚割ってしまったとします。本来ならば母親からしかられるべきなのに、妙にやさしくされたりすると、かえって心が痛むもんですよね。こういう時のやさしさがcruel kindnessですよ。でしょう?」
「まあ、そのようなことでしょうね。それで、ロブソンさんは、この高級娼婦がoxymoronだと言いたいわけですか?」
「その通り」
「そうでしょうか?昔の吉原に関する本を読むと、娼婦には階級があったと書いてありますよ。だから、高級娼婦や低級娼婦が居たということは事実でしょう?」
「そう言われてみれば、そうなんだけれど。。。」
「だから、高級娼婦という言い方に不自然なところはないと思います」
「そうかもしれない。でも、僕にとっては娼婦は娼婦なんだよね。昔の吉原には、確かに、娼婦には階級があった。だから、高級な娼婦という言い方も不思議ではないかもしれない。でもね、僕には高級な泥棒とか低級な泥棒と言うのと同じように聞こえるんですよ。泥棒に高級も低級もないよね。泥棒は人間として低級なんですよ」
「つまり、娼婦は高級娼婦でも、人間として低級だと。。。そういうことですか?」
「僕はそういう印象を持つんですよ。だから、高級な娼婦アメニアとしても、アメニアさんが低級な人間のイメージとして登場することになる。それでは、この物語の中のアメニアさんのイメージとは全くかけ離れてしまうんですよ。それで、高級娼婦という日本語は使いたくなかったんですよ」
「でも、それはロブソンさんの個人的な受け止め方でしょう?他の人には違和感はないかも知れません。少なくとも私には違和感がありません」
「ジューンさんは日本で育っていないから、娼婦という言葉のイメージが英語のwhore程悪い印象を与えないのかも知れない。でも、僕にとって、娼婦という言葉はwhoreと同じ響きを持つんですよ。だから、高級娼婦を僕の頭の中でイメージするとhigh-class whore という響きになるんです。これは、とてもじゃないけれど、いただけないんですよ」
「それもロブソンさんの個人的な解釈の仕方ではないのですか?」
「分かりました。ジューンさんが言うように、僕の個人的な受け止め方だとしましょう。でも、それとは別に、もうひとつ考えなければならないことがあるんですよ」
「なんですか?」
「コリンスのページで僕はすでに話したことなんだけれど、アクロコリンスにあるアフロディテ神殿でお勤めをした女たちは、娼婦というより巫女さんのような役割を持っていたと言ったでしょう。覚えていますか?」
「ええ、確かにそのように聞きました」
「クレタでも同じようなことが言えるんですよ。だから、娼婦という言葉を使うと本来のイメージが伝わらなくなってしまう。僕としては、この巫女的な要素を強調したいわけなんです。そのために、高級娼婦を使わずに美女アメニアとしたわけなんですよ」
「アメニアさんもアフロディテ神殿でお勤めをしたのですか?」
「いや、アフロディテ神殿ではなかった。でも、似たような神殿で大巫女さんになるための教育を受けた」
「似たような神殿というと。。。?」
“The palace of Knossos (クノッソス宮殿想像図)”
(この絵は一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「上の想像図は“クノッソス宮殿”と呼ばれているのだけれど、学者によるとこれは宮殿ではなく神殿だったと言う人も居るんですよ」
「つまり、アフロディテ神殿ですか?」
「いや、アフロディテと言う名前で呼ばれていたとは思わないけれど、クレタ島の女神であったことに間違いはないでしょう。むしろこのクレタ島の女神が西に伝わってキュテラ(Cythera)島の女神になったと僕は考えていますよ。つまり、キュテレイア(Cytheria)と呼ばれるようになったんです。これがアフロディテの別名ですよ」
「でも、キュテレイアはフェニキア人がもたらした女神だとロブソンさんは言ったじゃありませんか」
「そのとおり。フェニキア人の女神とクレタ島の女神が仲良く手を結んだと僕は見ていますよ」
「つまり、2つの女神が一緒になってキュテレイアと呼ばれるようになり、それがギリシャ本土でアフロディテと呼ばれるようになったと言うわけですか?」
「まさに、その通りですよ」
「そのように歴史書に書いてあるのですか?」
「いや、僕が言い出したことです」
「学会では認められていないのですね?」
「残念ながら認められていませんよ。僕はミノア文明学会の会員ではありませんからね。しがない歴史バカに過ぎませんよ」
「学会員になって発表すればいいじゃないですか?」
「何もそこまでして発表する必要はないですよ。やがて、この説を裏付ける遺物が出土すると僕は信じています。現在は、裏付けるものが何もないから、発表したって意味がありません」
「それで、アメニアさんは大巫女さんになるはずだったのですか?」
「そうなんですよ。10歳から12歳になると、大巫女さんになる女の子が10数人集められて、将来大巫女さんになるための教育がなされたんです。アメニアちゃんもその中の一人に選ばれたわけですよ」
「それが、どうしてcourtesanになってしまったのですか?」
「その辺のことが、僕の小説の中で語られているわけですよ。そこが面白いところなんです」
「そのことはここでは説明してくれないのですか?」
「それは、あとのお楽しみと言うことですよ」
「なんだか、もったいぶりますね」
「これはあくまでも導入部分ですからね。前書きがずいぶん長くなりましたが、これだけのことを話さないと、今から3500年前の話を急にしたって、面白くもなんともないですよ。でしょう?」
「言われてみれば、確かにそうですね。私も、アメニアちゃんが12歳で大巫女さんになる教育を受けたけれども、大巫女さんにはならなかった。たぶん、その辺になんとなく恋愛だとかセックスが絡んでくるような予感がしています」
「でしょう?これだけのことを話してくれば、たいていの人が興味を持ちますよ。クレタ島もずっと日本に近づいてくると言うものです」
「じゃあ、これから、いよいよ本文に入るわけですね?」
「そうです。期待してください」
「分かりました。大いに楽しみにしています」
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis7.html
きれいな写真がたくさん貼ってあります。ぜひ読んでみてください。
女が支配する国 [西洋史・オリエント史]
女が支配する国

「この絵の女性が大巫女さんですか?」
「いや、この女性は“蛇使いの女神(Snake Goddess)”のつもりです。でも大巫女さんもちょうどこのような格好をして儀式に臨みますよ」
「実際に蛇を使うのですか?」
「いや、実際には蛇を扱いません。蛇はシンボルですよ」
「何の?」
「蛇は女神のパートナーだったんです。つまり、クレタでは女性と蛇が神聖であり、男性は神聖とされなかったんですよ」
「蛇と女神が人間を創り出したということですか?」
「そういうことです。古代の言語は蛇にイヴと同じ名を与えたんです。この名は“生命”を意味しました。しかも、最も古い神話では最初のカップルは女神と男神ではなく、女神と蛇だったんですよ」
「男は全く神聖とは見なされていなかったということですか?」
「その通りです」
「どうして男性は神聖とはみなされなかったのですか?」
「それを説明するには経血について話さないとならないんですよ」
「経血って何ですか?」
「Menstrual bloodのことですよ」
「そういうことをこのサイトで話してもいいのですか?」
「もちろんですよ。これは真面目な科学的な話ですからね。人類の最古の文明時代より、子宮の中で“凝結”し、嬰児となる女性の血の中には、創造の神秘的な魔力があると考えられていたんです。男は聖なる恐れをいだいて男の経験とはまったく関係のない、不可解にも苦痛を伴わずに流されるこの経血を生命のエキスと見なしたんです」
「生命のエキスですか?」
「そうです。月経を表す語の多くは不可解、超自然的、神聖、精気、神性というようなものを意味しているそうですよ」
「英語にはそのような意味はなさそうですね」
「そうみたいね。僕が調べた限りではmonthと関係あると言うことだけしか分かりませんでしたよ」
「でも経血がそれほど重要視されていたのですか?」
「そうなんです。たとえば、ニュージーランドのマオリ族は、人間の霊魂は経血からつくられ、血が子宮に留められたときに人間の形をとり、成長して人になるのだと信じていたそうです。古代アフリカ人は経血が固まって人間をつくると信じていました。アリストテレスも同様に、人間の生命は経血の“凝固”からつくられると述べていますよ。プリニウスは経血を『発生のもとになる物質』と呼びました。経血が凝固物となることが可能で、時の経過にしたがって胎動を始めて、成長し嬰児となるものだと考えられていたようです。ヨーロッパの医学校でも18世紀になるまで、誕生前に経血が果たす機能について、そのように教えられていたそうですよ」
「マジで?」
「これは僕がでっち上げた話じゃないんですよ。歴史の本に書いてあった事をかいつまんで話したまでのことです」
「でも、月経中の女性はとりわけ差別を受けましたよね」
「それは母系社会から父系社会になってからの現象なんですよ」
「つまり、ずっと昔の母系社会では女性は経血のために神聖だと見なされていたわけですか?」
「そのとおりです。東洋と西洋の古代社会では、経血には氏族や種族の生命を伝える媒体であると言う考えがあったので、女性にはより権威があったんですよ」
「そうなんですか?」
「ジューンさん、信じられない、と言うような表情を浮かべていますね」
 「だって、ごく最近まで、例えばアメリカインディアンの女性など、ピリオドの時などは穢(けが)れていると言うことで小屋に隔離される風習があったんですよ。北米だけではありません。ヨーロッパでも、戒律の厳しいユダヤ教の一派など、男性は女性と握手しません」
「だって、ごく最近まで、例えばアメリカインディアンの女性など、ピリオドの時などは穢(けが)れていると言うことで小屋に隔離される風習があったんですよ。北米だけではありません。ヨーロッパでも、戒律の厳しいユダヤ教の一派など、男性は女性と握手しません」
「どういうわけで?」
「どうしてかと言うと、女性がピリオドかもしれないので、女性は穢れている。だから女性と握手しないと言うことですよ。女性の人間性を貶めていると思いませんか?」
「確かにそうかもしれない。女性の立場から見ればそう言いたくなるでしょうね。でも、それはさっきも言ったように母系社会から父系社会になったためなんですよ」
「母系社会というのはそれほど女性に権威があったのですか?」
「そうなんですよ。例えば、アフリカ西部の旧王国にアシャンティと呼ばれる国があったんですよ。この国の人たちの間では、女の子は“血”の運び手であるため、男の子よりも高く評価されたんです。つまり女の子が生まれることを望んだんです」
「ちょっと信じがたいですね。だって、中国でも日本でも100年ほど前までは“まぶく”風習があったでしょう?」
「良く知ってますね」
「それで、たいてい“まぶか”れるのは女の子と決まっていましたよね」
「そうです。父系社会では男の子のほうが大切ですからね。なぜなら、年を取ったら親は男の子に面倒を見てもらうわけですからね」
「母系社会では全く逆だったと言うわけですか?」
「そういうことです」
「いったい、誰がいつ母系社会を父系社会に変えたのですか?」
「ジューンさん、そんな怖い顔をして僕をにらまないでくださいよ。僕じゃないんだから」
「別にロブソンさんを責めているわけではありませんよ」
「それがクレタ島で起きたわけなんです」
「ほんとに?いつ頃ですか?」
「ミノア王の伝説が創られる前ですよ。ギリシャ本土からアカイア人がクレタ島にやってくる前です。つまり、紀元前14世紀までは母系社会だったんですよ」
「要するに、ギリシャ本土から父系社会のアカイア人がやって来て社会体制をすっかり変えてしまったと言うわけですか?」
「そうなんですよ。第二次大戦後、ソ連が東ヨーロッパに居ついて共産主義化したようなものです」
「それからずうっと世界的に父系社会になってしまったと言うわけですか?」
「そうです」
「マジで?」
「ジューンさんはマジが好きですね。僕の言うことが信用できませんか?」
「女性が神聖視されていた母系社会があったと言うことが、なんだか御伽噺(おとぎばなし)のようで。。。」
「でもね、ジューンさん、次の女たちをもう一度良く見てくださいよ」
Enthroned Birthing Goddess from Çatal Hüyük 5700 BC.
(The head was restored.)
“Venus of Malta”
“The Sleeping Venus of Malta”
(上のヴィーナスの写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「この“女神”たちは、実は母系社会を支えていた女たちを表わしているんですよ。見てください。堂々として頼もしい出(い)で立ちを!このぐらい逞しくないと一国を治めてゆけませんよ」
「でもちょっと太りすぎでは?」
「このぐらい貫禄がないと男を従わせてゆくことができませんよ。当然ですが、小さな諍いや小競(ぜ)り合いがあったでしょうからね。女プロレスラーぐらいの体力とバイタリティーがなかったら、いざと言うときに国をまとめてゆくことができません」
「つまり、これらの像は決して誇張したものではなくて、この女性たちの体型が一般的だったというのですか?」
「そう思いますね。なぜなら旧石器時代からこのようながっしりとした像が出土しているんですよ」
Venus of Willendorf (in Austria)
the famous venus of the Paleolithic Era (Old Stone Age)
(上のヴィーナスの写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「この右のずんぐりした像はいつ頃のものですか?」
「ヴィレンドルフのヴィーナスと呼ばれているのだけど、2万5千年から2万年前に作られたものだろうと言われています」
「このような女性が一般的だったというのですか?」
「少なくとも現在の女性のように瘠せてはいなかったと思いますね。とにかく太った女性が圧倒的に多い。太った女性ばかりをここで紹介しているわけではないんですよ」
「男性の像と言うのは出てこないのですか?」
「そう言われてみると、見たことないね」
「どうしてでしょうか?」
「つまりね、母系社会にあっては、前に言ったように男は神聖ではなかったんですよ。だから、女神の像はあっても男神の像はない。男神はいなかったから」
「ゼウスは?」
「あの神様は父系社会の神様なんですよ。上の女性たちから比べればずっと最近の神様なんですよ」
「ところで、男性はどのような体格をしていたのですか?」
「探したのだけれど、男性の像というのはなかなか見つからなかったんですよ」
「結局なかったのですか?」
「僕が調べた限りでは見つからなかった。その代わり壁画に男が描かれていましたよ」
「どんな壁画ですか?」
Cave painting in Lascaux, France.
(上の壁画はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「この写真がその壁画なんですよ。フランスのラスコーの洞窟の中に描かれたものです。上の一部を拡大したものが下に示したものです」
「この倒れている人物が男性というわけですか?」
「そうですよ、カリントウのようなおチンチンガ描いてあるでしょう?へへへへ。。。。」
「はははは。。。。(しばらくの間ジューンさんが笑います)。。。どうも、失礼いたしました」
「いいですよ。どんどん思う存分笑ってください。全くこれでは漫画ですよね」
「でも、これって、マジで男性ですか?」
「そうですよ。人間以外の生き物に見えますか?」
「でも、顔のあたりがちょっと変でしょう?」
「これはね、鳥のお面をかぶったシャーマンじゃないかと言う学者が居るんですよ。確かに、クチバシの長い鳥のお面をかぶっていると言われれば、そのようにも見えますからね。しかも、その当時はシャーマンが狩猟の安全と獲物(えもの)がうまく獲(と)れるように、まじないのようなことをしたでしょうからね」
「でも、これでは上の女性たちと比べてあまりにも簡単すぎますよ」
「だから、男はこの程度の存在でしかなかったんですよ。つまり女性は神聖だったから上のような女神の像が残っているのです。でも、男は全く価値のない存在だったので、このようにマッチ棒のような頼りない生き物として描かれているわけですよ。まさに女系社会だという証拠じゃないですか?僕はそう思いますね」
「生殖における男の役割ということは分かっていなかったのですか?」
「とにかく経血至上主義だったんですよ。人間は経血から生まれるということが当時の“科学”として信じられていたんです。だからこそ、女性は神聖だと考えら、そのために女系社会が保たれていたんです」
「しかし、男の役割ぐらい分かりそうなものじゃないですか?」
「でもね、外見上正常なカップルが結婚生活で満ち足りた性生活を営んでいても、10年間ぐらい子供が生まれない事って珍しい話ではないですよ。それでひょこりと10年ぐらいしてから生まれる、ということだってありますからね。現在のような科学知識で考えれば、生殖における男の役割という事については疑問の余地がありません。でもね、当時は誰もが太陽が地球の周りを回っていると信じていた時代ですよ。今のような医学知識は何もなかったんですよ」
「つまり、男は生殖に関して全く役立たずだと考えられていたわけですか?」
「そうですよ。そのことがこのページの一番上の“蛇使いの女神”によく表されていますよ。つまり、女神と蛇によって人間が作られたと信じられていたんです」
「男など必要なかったと思われていたのですか?」
「そうですよ。だからこそ、男はマッチ棒のような頼りない存在として描かれていたわけですよ。逞しい女神像と頼りない吹けば飛ぶような男の壁画。これらのことが、女系社会を雄弁に物語っていると思いませんか?」
「それで、クレタの女系社会は大巫女さんが王様のように君臨していたわけですか?」
「そうです。左の写真が大巫女さんと彼女に仕える男たちのフレスコ画です。紀元前1550年頃に描かれたものです」
「何をしているのですか?」
「すぐ下にクノッソス宮殿の想像図と、現在の宮殿遺跡の写真を示したのだけれど、この絵は宮殿の入り口の部屋の壁に書かれているものなんですよ。その一部です」
「行列の一部ですか?」
「そのとおりです。クレタ人も行列が好きなんですよ。なぜだか分かりますか?」
「分かりません。なぜですか?」
「エジプトの影響です。古代エジプト人も行列が好きなんですよね。何かというと行列をします」
「クレタとエジプトの間にはそれほどの交流があったのですか?」
「大有りだったんですよ。エジプト人が一番尊敬するのがクレタ人だったんです。エジプトとクレタの切っても切れない関係は、僕が小説の中でくどいほど書いています。ジューンさんは読んだんでしょう?」
「ええ、読みました」
「だったら、知っているでしょう?」
「そのようなことが書いてありましたか?」
「ありましたよ。どこを読んでいたのですか?エロい箇所だけを拾い読みしていたのですか?」
「そうじゃありません。でも、思い出せません」
「まあ、いいですよ。今度はじっくり読んでくださいね」
“The palace of Knossos (クノッソス宮殿想像図)”
“The ruins of the palace (クノッソス宮殿遺跡)”
“The procession to the Pharaoh's tomb (ファラオの墓へ副葬品を運ぶ行列)”
(上の写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「これはファラオの墓へ副葬品を運び入れる行列です。絵の書き方も良く似ているでしょう?」
「そうですね。ところで、大巫女さんはどうして胸をあらわにしているのですか?」
「儀式の時には例外なくオッパイを見せます。母系社会のシンボルですからね」
「でも、大巫女さんは体のほとんどを覆っているでしょう。なぜ胸だけを?」
「例えばね、ひ弱な男が背中を丸めるようにして歩いていたりすると体育の先生がハッパをかけるでしょう? “オイ、何だ、その格好は?もっと背すじを伸ばして胸を張って堂々と歩いたらどうだい” この大巫女さんはね、まさにそのように歩いているんですよ」
「つまり、女系社会だから、大巫女さんには権威がある。それで、わざわざ胸をあらわにし胸を張って正々堂々と歩いてゆく。そういうことですか?」
「そうだと思いますよ」
「でも、なんだかこじつけのようですね」
「だったら、この絵を見てどう思います?」
“The Madonna Litta painted in the 1480s by Leonardo da Vinci”
(上の写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「レオナルド・ダヴィンチによって描かれたマリア様ですね」
「そうです。どう思いますか?」
「イエス様である赤ちゃんにおっぱいを含ませているのですよね」
「そういうことです。この胸は母性を表していますよね。でも、上の大巫女さんの胸は母性と言うよりも母権あるいは女権を表しています。次の絵を見るともっと良く分かりますよ」
イギリス王 ヘンリー8世
(1491-1547)
スペイン王 チャールズ5世
(1500-1558)
(上の写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「これコッドピース (codpiece) でしょう?」
「良く知ってますね。さすがジューンさんですね」
「どういう意味ですか?」
「いや、別に意味を含めて言った訳じゃないですよ。ジューンさんの教養の深さを改めて知ったんですよ」
「なんだか、私、けなされているような。。。」
「いや、決してけなしているわけじゃありません。僕は素直にジューンさんの教養の深さに感心しているんですよ」
「このようなことで、感心しなくてもいいですよ。それで、上の写真から何が言いたのですか?」
「この二人の王様は明らかに父系社会の権威と言うよりも、むしろ“男”社会の権威をコッドピースで誇示していますよね。そう見えませんか?」
「そう言われてみれば。。。」
「でも、女性のおっぱいのようにむき出しにするわけには行きませんよ。でしょう?」
「(ジューンさん、笑いをこらえています。。。) それもそうですわね」
「そういうわけで、これまで見てきたようにクレタ文明と言うのは女系社会だと言うことが良く分かるんです。その女系社会の中心に大巫女さんが君臨していたと言うわけです」
「分かりました。それで、ロブソンさんの小説のヒロインですけれど。。。」
「アメニアさんのことね」
「ええ、そうです。そのヒロインは大巫女さんですか?」
「ジューンさんはすでに英語版を読んだんでしょう?」
「もちろん」
「だったら分かっているでしょう?」
「私はただ、これを初めて読む人の気持ちになってロブソンさんにお尋ねしているわけですよ」
「ああ、そうですか。分かりましたよ。じゃあね、ちょっと長くなりすぎたので次の機会に詳しく説明します」
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis6.html
きれいな写真や絵がたくさん貼ってありますのでぜひ読んでみてください。
クレタ島の美女 [西洋史・オリエント史]
クレタ島の美女
 「アフロディテが“性愛”の女神だったと言うのはちょっと意外でした」
「アフロディテが“性愛”の女神だったと言うのはちょっと意外でした」
「たいてい、愛の女神と言われていますからね。中世になってから“性”は脱落したんですよ」
「やはり“性”は隠さねばならないものと考えられたのですか?」
「そういうことですよ。ルネッサンスになって“性”がもう一度見直され、アフロディテの姿を借りてヌードが描かれるようになったというわけです」
「ところで、アフロディテがコリンスで生まれたのではないと言うことですが、どこで生まれたのですか?」
「最もよく知られている説に次のようなものがありますよ」
大地はつぎに、キュクロプス(円い目)とあだ名される恐ろしい怪物の息子たち(ブロンテス、ステロペス、アルゲス)を生みました。額の真ん中に円い目が一つついている巨神たちです。つづいてコットス、ブリアレオス、ギュゲスといったヘカトンケイル(百の手)を生みます。肩からは百の腕が伸び、五十の首が生えているといった不気味で恐ろしい姿の巨神たちです。
ウラノスは実の子でありながら、キュクロプスたち、ヘカトンケイルたちを最初から憎み、生まれると同時にみな大地の奥に隠してしまいました。怒ったのは母親ガイア(大地)です。金剛の大鎌を用意するとウラノスへの復讐をタイタンたちに訴えました。ひとりこれに応えたのが末っ子のクロノスで、大地は彼を待ち伏せの場所に隠し、大鎌を手渡しました。そしてウラノスがガイアとの交わりを求めておおいかぶさってきた時、息子クロノスは、すばやく父の陰部を刈り取り背後の海原に投げ捨てたのです。 流れる血潮を大地が浴びて生まれたのが、復讐の女神(エリニュスたち)と巨人(ギガスたち)でした。
ウラノスの陰部はしばらく海面に漂っていましたが、やがてそのまわりに白い泡が沸き立ち、そのなかからひとりの美しい乙女が生まれました。彼女は泡(アフロス)から生まれた女神ということで、アフロディテと呼ばれるようになりました。
Birth of Aphrodite by Alaxandre Cabanel (painted in 1863)
(この絵はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「このアフロディテが生まれたときの様子を描いたのが上の絵ですよ」
「上の誕生のお話はなんだかグロテスクで血なまぐさいですけれど、この上の絵はとてもそのような残虐な事件の後で生まれたようには思えないですね」
「芸術はロマンを追い求めますからね。海面に浮いている血まみれのペニスを描いたらロマンチックじゃなくなりますよ。へへへへ。。。。それでは、絵が台無しになってしまいますからね」
 「ハハハハ。。。(ここでジューンさん爆笑します) それもそうですわねェ」
「ハハハハ。。。(ここでジューンさん爆笑します) それもそうですわねェ」
「アフロディテはね、もともと古代ギリシャとは関係がなかったんですよ」
「ギリシャの女神ではないということですか?」
「その通りです」
「でも、ロブソンさんはアフロディテは古代ギリシャの女神だと。。。」
「そうですよ。確かにそう言いました。それが通説ですからね。でもね、アフロディテがローマでヴィーナスとなったように、もともとはオリエントからやって来た縁もゆかりもない女神がアフロディテとして古代ギリシャの女神になったんですよ」
「オリエントというとメソポタミアのあたりですね」
「そうです」
「それで、アフロディテは一体どこで生まれたのですか?」
「現在最も知られている説ではキプロスの海で生まれたということになっていますよ」
「キプロス?」
「英語圏の人にはサイプロスと言わないと通じないんだよねェ~」
「ああ、Cyprusですか。それなら分かりますよ」
「サイプロスのどこで生まれたのですか?」
「Paphos(パフォス)ですよ」
「ギリシャから、かなり離れてますね」
「でもね、このサイプロスには紀元前14世紀から13世紀にかけて、ギリシャのペロポネソス半島のアルゴス地方から古代ギリシャ人の一部族アカイア人がやってきて植民地にしたんですよ」
「随分昔の話ですね」
「確かにかなり昔のことだけれど、僕が書いた小説は紀元前16世紀の頃から始まるんですよ」
「そんな大昔の事を書いたのですか?」
「そうですよ。ジューンさん、なんだか呆れた顔して僕を見てますね」
「だって、そんな昔のことが分かりますか?」
「分かりますよ。古代エジプトや初期のクレタ文明から考えれば、まだ最近ですよ。何しろ紀元前26世紀の頃から栄えたんですからね」
「それで、アフロディテはどうしてパフォスで生まれたのですか?」
「アカイア人が最初に住み着いたのがこのパフォスなんですよ。今でも郊外にアフロディテ神殿の遺跡があります。伝説ではすぐ下の写真(一番下のリンクをクリックすると見れます)のトラトゥミュウの海岸で生まれたことになっています。大きな岩が海に浮かんでいるでしょう。あのあたりでアフロディテが誕生したことになっているんですよ」
「マジで?」
「もちろんですよ。僕がでっち上げた話ではありません。」
「でも、どうしてここで?」
「最初に住み着いた人が航海の守り神としてのアフロディテを祭ったわけですよ」
「それで、もともとは何と言う女神だったのですか?」
「オリエントの豊穣多産の女神アスタルテとかイシュタルと起源を同じくする女神だったらしい」
「らしい、ということは特定できないということですか?」
「そういうことです。僕はむしろ豊穣多産の女神であるよりもフェニキア人がもたらした航海安全を司る女神だと思っています」
「それはなぜ?」
「実はアフロディテの別名はキュテレイアと呼ばれているんです」
「どういう意味なんですか?」
「フェニキア人の女神なんですよ。英語ではCythereaとかCytheriaと書きます。上の地図で見ればわかりますがペロポネソス半島の先に小さな島があります。Cytheraと書いてキュテラと読みます。キュテレイアというのはキュテラ島の女神という意味なんです」
「つまり、フェニキア人の航海安全の女神がアフロディテの元祖ということですか?」
「僕はそう見ています」
「では、サイプロスのアフロディテとは関係ないのですか?」
「おそらく同じ女神でしょう?伝説では、サイプラスで生まれたアフロディテを三美神(The Three Graces)がキュテラ島で迎えて、それからオリンパスの山へ案内したことになっていますよ」
「なんだか、こじつけたようですね?」
「伝説というのは、そういうものじゃないですか」
「それで、ロブソンさんはアフロディテは航海安全の女神だと言うわけですか?」
「そうです。だからこそコリンス市民も抵抗なく自分たちの守り神として迎えることができたんでしょうね。とにかく交易によって富を築いた町ですからね。航海安全をもたらしてくれる女神はありがたいはずですよ」
「しかし、その説明ではクレタ島が出てきませんね?」
「気付きましたか?」
「ええ、まだ何かあるのでしょう?」
「そのとおり。うえの地図をもう一度良く見てください。伝説ではサイプラスで生まれたアフロディテを三美神がキュテラ島で迎えたことになっています。何か不自然だと感じませんか?」
「別に。。。」
「アフロディテはサイプラスからキュテラ島へ寄ってそれからオリンパスの山へ行ったことになっています。でも上の地図を見れば一目瞭然のことですが、当然クレタ島にも寄ったはずですよね」
「確かにその方が自然ですね」
「むしろ、上の地図で見るような小さな島、キュテラ島の女神よりもクレタ島の女神の方が功徳があると思いませんか?」
「そうですね」
「クレタ島の文明はミノア文明と呼ばれるのですが、この文明は海洋文明だったんですね。紀元前18世紀から紀元前16世紀にかけて大繁栄したんですよ。コリンスの富など比べようもない程この島は海洋王国として栄えたんです。だから、コリンスが航海安全の女神を必要とするなら、クレタ島の女神を迎えた方がよっぽど理にかなっているんです」
「では、なぜクレタ島の女神を迎えなかったのですか?」
「本当はクレタ島の女神を迎えたかったんですよ。でもね、クレタ島の女神は女上位の女神だったんです。つまり、古代ギリシャのような男上位の社会にはふさわしくなかったんですよ」
「マジですか?」
「ジューンさん、僕が話すことをあまり信用していないようですね?」
「だって、ロブソンさんは時々マジでおかしなことを言いますからね。気をつけてかからないと。。。」
「確かに用心することに越したことはありませんけれど、この話に関する限り、僕はマジですよ」
「では、他の話はフマジですか?」
「フマジって言い方はないと思うなあああ。。。」
「だって、不真面目って言うでしょう。だからマジの反対はフマジ。。。ふふふふ。。。」
「まあ、いいですよ。そのうちその言葉が日本ではやるかも知れませんよ。とにかく、これから僕が話すことにフマジなし」
「分かりました。それで、クレタ島の女神って本当に女上位だったのですか?」
「そうなんですよ。とにかく女性のパラダイスのような王国だったんです。女神の国と言った方がふさわしいくらいですよ」
「そうなんですか?例えばどのようなところが?」

“Ladies in Blue”—fresco from Knossos, 16th century BC.
「上の写真に見るとおり、今から4000年前のクレタ島の女性は、結構ナウい、ファッショナブルな女だったんですよ。クレタ文明を発掘した考古学者アーサー・エヴァンズがフレスコ画に描かれていた彼女たちを見て、思わず“可愛いパリジェンヌ”と叫んだというエピソードが伝わっているほどです。4000年前とは思えないほど現代的なセンスを持っていると思いませんか?」
「言われてみれば確かに現代的なファッションを感じさせますね」
「でしょう?」

「全身を表すとこんな感じになりますよ。どうですか?」
「ちょっとスカートが長すぎるようですね」
「確かに長いですよ。でもね、19世紀のパリの本物のパリジェンヌと比べてみてください」
「どちらの女性と喫茶店に入りたいですか?と問われれば、僕はおそらくクレタ島の女性に声をかけるでしょうね」
「そうですか?」
「そうですよ。第一、こんなでかい幅広のスカートをはいた女性と喫茶店へ入ってみてくださいよ。周りの人が迷惑そうな顔をしますよ」
「確かに、近頃の喫茶店ではテーブルが、バタバタと倒れてしまうでしょうね」
「とにかく、上の二人の格好を見比べると19世紀のパリジェンヌの方がダサいですよ。クレタ島の女性の方がモダンな感じがしませんか?」
「そうですね。。。」

「19世紀の女性と比較するのでは、時代が違いすぎるので、同じ時代のエジプトの女性と比べてみましょう。次の絵の中の女性たちは今から3500年から3000年前の服装をしています。上のクレタ島の“パリジェンヌ”とほぼ同じ時代です」

「一目見ただけでも、エジプトの女性の方がシンプルですよね。。。というか、言葉は悪いですが“土人スタイル”ですよね。クレタの女たちよりも原始的な感じがします。我々の眼には、どう見てもクレタ島の女性の方が現代的な印象を与えます。そう思いませんか?」
「確かにこの写真で比べるとそうですね」
「僕がクレタ文明にロマンを感じるのはそのような理由ですよ。ヘアスタイルといい現代風なスカートといいセックスアピールする胴着といい、19世紀のパリジェンヌよりもパリジェンヌらしいところがありますよ」
「フープ・スカートは、どう見ても時代遅れなので、そのように映るのではないですか?」
「それだけじゃなくて、例えば当時上流社会で流行していた胸を見せる短い胴着(bolero)を身に着けていますよ。当時も細いウエストが好まれたそうです」
「確かにファッションを見ると現代的なところがありますね。でも、それだけでは女性のパラダイス、女神の国とは言えないのではないですか?」
「もちろん、それだけで決め付けるつもりはありません。他にも理由があるんですよ」
「どんな?」
「クレタ文明が栄えた紀元前18世紀から16世紀には実権を持っていたのは王ではなく大巫女だったんだ」
「大巫女ですか?」
「そう。英語で言うならHigh priestessですよ」
「つまり女王ということですか?」
「女性だから、女王と言ってもいいんだけれど、やはり宗教的な性格が強かったらしい。中世のローマ法王のような権力を持っていたと思えば間違いないよ」
「王様は居なかったのですか?」
「形式的な王様は居たらしい。でも、実権はなかったようです」
「でも、ミノアと言う名前はそもそも王様の名前でしょう?」
「そのとおりです。ジューンさんの質問に答えますが、その前に、ここでざっとミノア文明の歴史を見てください」
紀元前1700年頃に大地震があって、すべての宮殿が崩壊しました。しかし、やがて元の宮殿の場所に、さらに規模が大きな華麗な宮殿がたてられました。その大地震後を新宮殿時代と呼びます。現在、私たちが考古学博物館で目にするミノア時代の出土品は、この新宮殿時代のものがほとんどです。
紀元前1600年頃には、各都市国家の中央集権化、階層化が進み、クノッソス、ファイストスが島中央部を、マリアが島東部をそれぞれ支配するようになりました。
クレタでは4つの大きな宮殿が発見されており、なかでもクノッソスが主導権を握っていました。新宮殿時代の末期、紀元前1500年頃にサントリーニ(Thera)島で大噴火があり、ミノア文明の力が衰えたのに乗じて紀元前1400年頃ミュケナイのアカイア人がクレタ島に侵入、文化財や貴重な物は略奪されたり破壊されたりして、それ以降クレタ文明は衰退に向かいました。その時代も含めて紀元前1200年までをミノア時代と言います。クノッソス遺跡を発掘したアーサー・エヴァンズが神話伝説に出てくるミノス王の名を取ってミノア文明と名付けたのです。
「これがクレタ文明の略歴ですよ。これを見てもらうと分かるのですが、“紀元前1400年頃ミュケナイ(ギリシャ本土)のアカイア人がクレタ島に侵入”したと言うことが書いてあるでしょう?」
「ええ、確か同じ頃にアカイア人はサイプラスにも移住して行ったのですよね」
「その通りです。この時期に人類が大移動を起こしているんですよ」
「どうして?」
「まだはっきりとは分かっていないのだけれど、どうやら気候と関連があるというようなことが言われているんですよ」
「気候と言うと?」
「この頃、今から3500年前、地球全体が寒冷期になって作物が取れなくなった。それで人類が南下してきた」
「それでアカイア人はクレタ島やサイプラスへ移住したと言うわけですか?」
「北から戦争に強い人たちがやってきたから、押し出されるような形になったんですよ。そのように考えている歴史家も大勢います」
「つまり、大噴火のためにミノア文明が衰えているところに、アカイア人がやってきて、クレタ島がのっとられたと言うわけですか?」
「早い話が、そういうことなんですよ。それまではね、クレタ島は母系社会だったんです。話せば長くなるんですが、紀元前4000年頃までは、ヨーロッパは全域にわたって母系社会だったんですよ」
「どうしてそのようなことが言えるのですか?」
「実は、他のページにこのことを書いたんですよ。でも、英語なんです。まだ訳していません。とりあえず、写真だけここに貼り付けます」
Enthroned Birthing Goddess from Çatal Hüyük 5700 BC.
(The head was restored.)
(この絵はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「わああ、すごーく太った女性が出てきましたね」
「この女神は紀元前5700年頃、人が住んでいたチャタル・ヒュユク(Çatal Hüyük)と呼ばれる集落の遺跡から出てきたんですよ。場所は上の地図の小アジアの中に見つけることができます」
「この女神が出てきたから母系社会だというのですか?」
「この女神だけじゃなく、とにかく圧倒的に女神が多いんですよ。ジューンさんはこの小アジアがアナトリア(Anatolia)と呼ばれていることを知っているでしょう?」
「ええ、知ってますよ」
「じゃあ、その意味は何だと思いますか?」
「意味があるのですか?」
「あるんですよ。“女神がたくさん居る土地”と言う意味なんです。とにかく母系社会だということを考古学者が出土品からも確認しています」
「アナトリア以外からもこのような女神は出てきたのですか?」
「マルタ島からも見つかっています」
“Venus of Malta”
“The Sleeping Venus of Malta”
(上の2つの写真はこの記事の一番下のリンクをクリックすると見ることができます)
「マルタ文明もやはり母系社会だったのですか?」
「そうです」
「それがどうして父系社会になってしまったのですか?」
「すでに言ったように、紀元前4000年頃を境にヨーロッパには人類の大移動があったんですよ」
「やはり気候と関係あるのですか?」
「そうらしい。この時は半農半牧を営むインド=ヨーロッパ語族の祖先がヨーロッパ中・東部に侵入・定住したんです。ジューンさんの遠い祖先の皆さんですよ。もちろんこの人たちは現在と同様、父系社会を形成していました」
「そうなんですか?」
「そうですよ。現在は男女同権といわれていますが、基本的には父系社会ですよね。たいてい父系の姓を名乗ります。この父系社会というのは戦争が強いんです。アナトリアの社会でもクレタの社会でも、大きな戦争と言うものがなかった。その事は遺跡からも確認されています」
「つまり戦いに弱い母系社会は戦争に強い父系社会の集団に追われるような形でクレタ島やマルタ島に移り住んだと言うわけですか?」
「そういうことです」
「では、クレタ島のミノア王はどう説明されるのですか?」
「ミノア王の伝説はアカイア人がギリシャ本土から乗っ取りに来てからできた話なんですよ。それまではミノア王みたいな男の権力者は居なかったんです」
「つまり、大巫女さんが実権を握っていたと言うわけですか?」
「その通りですよ」
「その大巫女さんと言うのは一体どのような人なのですか?」
「ちょっと、長くなりましたから、それは次の機会に説明しますね」
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis5.html
きれいな写真がたくさん貼ってあります。ぜひ読んでみてください。
美女の神殿 [西洋史・オリエント史]
美女の神殿
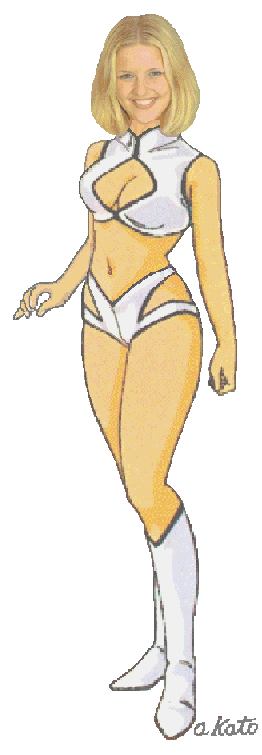
「ロブソンさん、なんだかとてもまぶしい絵を貼り付けましたね」
「ジューンさん、この記事ではあなたの写真を貼り付けたんですよ」
「あら、いやだ、ほんとうにィ。。。どうしてあたしの写真など貼り付けたんですの?」
「この記事にあの絵を貼り付けるのは問題があると思ったんでね。。。今すぐに見たい人はこの記事の一番下にリンクを貼り付けてありますからね。それをクリックして見てくださいね。ところで、ジューンさんは絵を見てどんな印象を持ちましたか?」
「そうですね。なんだかハッとさせられるような絵ですね」
「その絵は今から140年以上も前に描かれたんですよ。ごく最近描かれたと言っても十分に通用するでしょうね」
「私は絵のことはあまり分かりませんけれど、キューピッドを描く人は最近ではあまりいないのではないですか?私は、キューピッドが宙に浮いているのを見てイタリアのルネッサンスの頃に描かれたのではないかと思ったくらいです」
「ほォ~~~、ジューンさん、絵のことには詳しくないと言いながら、けっこう知ってますね。僕より詳しいのじゃないですか?」
「いえ、それ以上のことは知りません。でも、140年前に描かれたということはちょっと信じがたいですね」
「どうして?」
「1863年に上の絵は描かれたんでしょう?ということはアメリカでは南北戦争の真っ最中ですよ」
「その絵を描いたアレクサンダー・カバネルはフランス人ですよ。だから戦争とは縁がなかったんですよ」
「私が驚くのは、こんなヌードがよく問題にならなかったと思って。。。当時、アメリカやカナダでなら展示禁止になったかもしれませんよね?」
「恐らくジューンさんも、そう言うだろうなと思ってこの絵を貼り付けたんですよ」
「パリだから問題にならなかったのですか?」
「そうではないですよ。パリだから問題にならなかったんじゃなくて、この絵の中の裸の女がアフロディテだから問題にならなかったんですよ。もし、この絵の女がパリのカフェのウエイトレスだったら、大問題になったはずですよ」
「どうしてですか?」
「僕が前のページで言ったように、『オディッセイ』を調べているうちに、この大叙事詩が欧米人の原点のような気がしてきたんですよ。つまり、現代欧米文明は古代ギリシャ文明、古代ローマ文明から営々と続いていると考えている人が多いんだよね。だから、上の絵が描かれた当時、フランスやイギリスの大学では、古代ギリシャ古代ローマの古典をとにかく飽きるほど勉強させられた。そういうわけで、『オディッセイ』を暗記するほど勉強する人も珍しくなかった。つまり、ギリシャの古典やローマの古典は必須科目だったわけですよ。だから、上の絵の女がアフロディテだから問題にならなかったんです」
「そうでしょうか?」
「ジューンさん、僕がでたらめを言っているとでも思ってるの?」
「そういうわけではないですけれど。。。」
「オリジナルの記事の次の絵はイタリア・ルネッサンスの巨匠ティツィアーノ(Tiziano)が1548年に描いたんですよ。アメリカもカナダもまだ出来ていない時代です。日本は戦国時代でした。1548年という年は織田信長と濃姫が結婚した年です。もし、この絵が日本で展示されたら、戦争などほっぽりだしてビックリしたでしょうね。では、なぜ、イタリアのルネッサンスで、このヌードが問題にならなかったのか?それは、この絵の中の女がアフロディテだったからですよ。」
「そうでしょうか?」
「ジューンさん、疑い深いですね。それ以外に答えはありませんよ。そもそもルネッサンスと言うこと自体がギリシャの古典を改めて認識するということでしたからね。この伝統がカバネルが上の絵を描いた頃にも引き継がれていたわけですよ。だから、アフロディテのヌードをポルノなどと言って騒いだら、その人こそ女神を冒涜する者として教養のない愚か者とみなされたわけですよ」
「ちょっと信じがたいですけれど。。。」
「ジューンさん、無理して僕の言うことに疑いを挟むことはないですよ。ジューンさんだってルネッサンスのことはよく知っているでしょう?」
「ええ、知っていますよ。一応勉強させられましたから。。。」
「でしょう?」
「でも、アフロディテのヌードが、なぜ許されたのかまでは説明をよく聞きませんでした」
「ジューンさんがサボって、聞きはぐってしまったんですよ。とにかく、そのような風潮が西洋のルネッサンスにできあがったんです。いわゆるエリートの中ではそのように考えることがあたりまえになったんですよ。つまり、アフロディテのヌードをポルノだと決め付けることはダサいと思われたわけですよ。ギリシャの古典を知っていれば、アフロディテが愛の女神である事を知っている。その愛の女神が裸であっても決して可笑しいことではない。そのことを問題にして、口うるさい無知なオバタリアンのように騒ぎ立てることはみっともないという気風が出来上がったわけです」
「そうなんですか?」
「そうなんですよ。それ程ギリシャ古典は当時のエリートにとって金科玉条のごとくに考えられていたわけです」
「つまり、アフロディテは古代ギリシャの愛の女神だった。その女神が裸であることは神聖なことであった。だから、ルネッサンス当時、裸のアフロディテを描くことは問題にならなかった。そう言うことですか?」
「その通りですよ」
「。。。」
「ジューンさん、なんだかまだ納得がゆかないようですね?」
「あの絵の中のオルガンを弾いている男の人ねェ。。。」
「うん、オルガニストが居ますよ。その男がどうかしましたか?」
「あの人、わき見をしながら弾いていますよね。しかも、ちょっとあなた、どこを見ながら弾いているの?と問いかけたくなるような見方をしていますよ」
「ジューンさん、なかなかいいところに気が付きましたね。へへへへ。。。。」
「何ですか、その可笑しな笑いは?」
「いや、失礼いたしました。でも、言われてみると、確かにオルガン弾きはかなりじっくりと、しかも大胆にアフロディテのあそこを覗いていますよね。彼女がキューピッドと話をして気を奪われているのをいいことに、かなり大胆に覗いていますよ。僕も、オルガニストと同じ状況に置かれたら、同じようにすると思いますよ。へへへへ。。。。」
「でも、この画家は、どうしてそのようないやらしい男を描いたのですか?」
「美術書などを見ると、この絵はallegorical workだと書いてあるのが多いですよ」
「寓話的な作品だということですか?」
「その通りですよ」
「どこが?」
「ジューンさんがこのオルガン弾きの男のことをいやらしい、と言ったけれど、まさにそこのところに僕は寓話的なものを感じるのですよ」
「どういうことですか?」
「このティツィアーノという巨匠は長生きした人なんですよ。生まれたのが1490年。上の絵を描いたのが1548年だから、58歳の時に描いたわけですよ」
「随分年をとってから描いたんですね」
「確かに若くはない。だから、とりわけ裸の女を描く必要はないんですよ。僕なら、真っ裸の女より薄い下着を身にまとった女のほうがよっぽどエロっぽく感じられますよ」
「それなのにどうしてこの画家は裸のアフロディテを描いたのですか?」
「この絵を描いた当時、このティツィアーノはすでに巨匠としての名声を築いていた。だから、この画家が描く物は誰も正面きって非難することは出来なかったでしょう。そういうわけで、僕はこの絵に風刺的なものを見るんですよ」
「どこが風刺なのですか?」
「ジューンさんはガリレオの宗教裁判を知っているでしょう?」
「ええ、知ってますよ」
「ガリレオ・ガリレイは1564年にイタリアのピサで生まれ1642年に亡くなっている。ティツィアーノが1576年にベニスでなくなった時、ガリレオは12歳だったと言うわけですよ」
「ガリレオとティツィアーノの間には何か関係があるのですか?」
「直接の関係はない。でも二人とも宗教界に対してはあまりいい印象は持っていなかったはず。上の絵に僕はティツィアーノの宗教界に対する風刺を見るんですよ。この当時の宗教界と言うのはほとんど絶対的な権威を誇示していた。そのことがガリレオの宗教裁判に実によく表れている。ガリレオは、1632年に論文『天文対話』の中で『地動説理論』を発表したんですよ。そのために宗教裁判にかけられた。これはジューンさんも知っての通り。『地球は動いていない』と言わされ、やっと命は助かった。しかし、彼は有罪になった」
「でも地動説は正しかったのですよね」
「もちろん、そうですよ。小学生でも地球が太陽の周りを回っている事を知っていますよ。でもローマの法王庁はそれを認めなかった」
「天動説を通したのですか?」
「そうですよ」
「ウッソォー」
「ガリレオの死後350年たった1983年(昭和58年)に宗教裁判で有罪となったガリレオ・ガリレイに対してローマ法王ヨハネ・パウロ2世がやっと宗教裁判の誤りを認めて謝罪したんです」
「マジで?」
「もちろんですよ。僕はマジですよ。これは事実なんですよ」
「なんだか笑い話のようですね?」
「笑えない笑い話ですよ。それ程宗教界の権威と言うのはすごかったんですよ」
「それで、上の絵のどこが風刺なんですか?」
「ジューンさんにはまだ分かりませんか?」
「分かりません。どういうことですか?」
「つまりね、アフロディテとキューピッドを描いていることになっていますが、あれは、当時のごく普通の女と子供を描いたんですよ。アフロディテを描いたんじゃありませんよ」
「どうしてそうはっきり言えるのですか?」
「もし、本当にアフロディテを描いたのなら、キューピッドはちょうど一番上の絵のように背中に羽が生えて居なければならないんですよ。ジューンさんも言ったでしょう。キューピッドが宙に浮いているから、あの絵がルネッサンス時代に描かれたものかと思ったと。。。」
「その通りです」
「一番上の絵を見れば、誰が見ても宙に浮いている子供はキューピッドに見えますよ。でも、ティツィアーノが描いた絵を見てください。誰も何も説明しなければ、これはどう見ても裸の女を描いたものですよ。よく見ると子供の背中に羽らしき物が生えているけれど、キューピッドだと聞いて初めて、羽が申し訳程度に生えている、ということが分かるんですよ。つまり、言い訳のために、不自然な羽をちょっと描き添えている。そうじゃないと、ガリレオのように宗教裁判にかけられてしまいますからね」
「つまり、ティツィアーノはアフロディテと見せかけて、ごく普通の裸の女を描いたというわけですか?」
「その通りですよ。アフロディテをモチーフに書きたいのなら、次の絵のようにキューピッドをもっとはっきりと描きますよ」
Mercury with Venus and Cupid by Correggio (1489-1534)
(painted in c.1525)
(オリジナルの記事の中で見てください)
「これなら、キューピッドの他にマーキュリーもいますからね、この女が普通の女ではなくアフロディテ(ヴィーナス)だということも、すごく納得がゆきますよ。また次の彫刻などもキューピッドが宙に浮いているし、パン(pan)が居るから、これも普通の女ではなくアフロディテであることが納得ゆきます」
A marble statue of Aphrodite, Pan, and Cupid
in the National Museum of Athens.
(オリジナルの記事の中で見てください)
「この上の2つの作品とこのページの一番上の絵を見れば、どれもが現実離れしている。つまり神話の世界のことだと言う事が一目見れば想像が付きます。でも、ティツィアーノが描いた絵はとても神話の世界とは思えませんよね」
Aphrodite (Venus) with Organist and Cupid
by Tiziano Vecellio (painted in 1548)
(オリジナルの記事の中で見てください)
「キューピッドは絵の片隅に追いやられてしまっている。羽もほとんど見えません。むしろ分からないように描いている。しかも、このオルガン弾きなどは、全く神話とは関係ない人物ですよ。アポロでもないし、マーキュリーでもないし、パンでもない。つまり、ごく普通のオルガン弾きです」
「要するにティツィアーノは神話の世界からも宗教的な権威からも無関係なところで普通の裸婦を描きたかったというわけですか?」
「そうですよ。このオルガン弾きこそティツィアーノ自身ではないかと僕は思っているんですよ。つまりね、豊艶な女が素っ裸で横たわっていれば、男のごく自然な関心として、その女のあそこはいったいどうなっているんだろう、という単純な興味が沸き起こる。それをティツィアーノは恥も外聞もなく描いているんですよ。ルネッサンスは本来神話とも宗教とも関係のない自然体のものではないのか?ティツィアーノはこの絵を通してそう言っているのではないか?僕はそう思っているんですよ」
「ところで、このページの副題であるアフロディテ神殿とどういう関係があるのですか?」
「そうでした。その事を説明するためにこのページを書き始めたんです。ストラボンがコリンスで見聞した驚きはまさにティツィアーノが絵の中のオルガン弾きとして感じた驚きだったはずです」
「ストラボンはどのような事を見聞したのですか?」
「彼は『地理誌』の中で次のように書いているんですよ」
–Strabo “Geography” 8.6.20-23
「この女神に使える女たちがプロスティチュートだったわけですか?」
「歴史書にはたいていそのように書いてありますよ。でも、日本語の娼婦とか売春婦と言うイメージではないんですよ。英語のwhoreとも違うんです」
「どういう風に?」
「前にも書いたように、巫女さんに近い役割を持っていたんです。つまり、女神に仕えると本心から思っていた女性が多かった」
「アフロディテに仕えるとは具体的にはどういうことなんですか?」
「これも、話し始めると長くなるんですがね、はしょっていえば、この巫女さんたちはアフロディテの代理人として信者の身と心を癒してあげたんですよ」
「身と心を癒してあげる、というと言葉は綺麗に聞こえるのですけれど、結局のところセックスするということなのでしょう?」
「そう言ってしまうと身も蓋もないんですよ。でも、結局そういう事なんですよ。この当時は戦争が多かったから、戦いで身も心も傷ついた人が神殿に身を寄せたんですよ。つまり、病院の機能も兼ね備えていたんです。だから、この巫女さんたちは、ある意味では女医でもあり、女性心理療法士でもあったわけですよ。現在ではセックスするという言い方しかないだけれど、むしろmake love ということですよ。『性愛する』という言い方は無いですよね。でも、それに近いですよ」
「私には、まだよく分かりません。」
「ジューンさんがよく分かるように一つのエピソードを話します。ストラボンがコリンスを訪ねたときにはもう廃れてしまった風習になっていたようですが、この町の揺籃期にはすべての女性はアフロディテ神殿でお勤めを果たさなければならなかったのです」
「どのような?」
「つまり、どんなに裕福な女でも、また貧しい女でも、神殿に身を寄せて信者と契りを交わす必要があったんです。美しい女はすぐに信者が選ぶので1日でお勤めを果たせるのだけれど、醜い女だと、なかなか信者が寄り付かず、半年や1年近くも神殿で生活しなければならないと言うこともあったらしい。お勤めが果たせるまで神殿に居なければならなかったわけです」
「つまり信者と性交渉を持つことがお勤めだったわけですか?」
「そうですよ。アフロディテにかわって信者を癒してあげるわけだから、信者はサービスを受けたあとでお賽銭を上げるわけですよね。それが神殿の収入になるわけです。しかし、いつの頃からか専属の女が神殿に住みつき始めたというわけです。そう言うわけで、ストラボンがコリンスを訪れた頃には専属の女が千人以上居たというわけですよ」
「その専属の女たちは、現在で言うなら、アムステルダムの飾り窓の女たちと変わらないわけでしょう?」
「全く違いますよ。そうではないんです。」
「どこがどう違うのですか?」
「つまり、たとえて言えば、ローマ法王が居るバチカン市国の庁舎に飾り窓の女を移住させて、そこに住まわせ、そこで敬虔な信者と宗教的な法悦に浸る。たとえて言えば、そういう事なんですよ」
「つまり、神聖な行為だったと言いたいわけですか?」
「その通りですよ。現在とは考え方が全く異なっていたんですよ。だからこそアフロディテ神殿で性愛の交歓がなされたわけですよ。現在の法王庁で、飾り窓の女が性愛の饗宴をしたら大変なことになるでしょう?でも、コリンスの揺籃期にはそれが“巫女さん”たちの“神聖な”お勤めだったんですよ」
「アフロディテ神殿というのは、そのような事をするために立てられたのですか?」
「そうじゃないですよ。もちろん、アフロディテを祭るためですよ。アフロディテは愛の女神といわれているけれど、当時はむしろ“性愛”の女神だったんですよ。現在は“性”と“愛”が切り離されてしまったけれど、その当時はこの両者は混然としていた。これが切り離されたのが言って見れが中世ですよ。そしてルネッサンスになって、この切り離されていた性と愛をもう一度結びつけるような動きが出てきた。これを象徴しているのがティツィアーノが描いた上のオルガン弾きですよ。僕はそのように、あの絵を見ています」
「なんだか急にお話が飛躍しましたね。。。」
「とにかくね、このアフロディテ神殿がコリンスの市街を見下ろす丘の頂上(アクロコリンス)に建っていたんですよ。現在は、見る影もなく残骸すら残っていないのですが、おそらくアテネのアクロポリスにあるような神殿が建っていたでしょう。“性愛”の女神が神殿の中に祭られていたかもしれません」
「うわー、なんだかすごいですね。本当にこのようなアフロディテ像が立っていたのですか?」
「これは僕が考えた想像図ですよ。実際にはどのような像だったか分かりません。とにかく、アフロディテ神殿が一等地に陣取っていたのは事実なんです。これだけを取ってみても、“性愛”が古代コリント市民にとって、いかに重要であったかが分かるというものです。そしてこの“性愛”を象徴しているのがティツィアーノが描いた絵の中の女ですよ。オルガン弾きがしみじみと覗いていますが、それこそ、古代ギリシャの性愛を見ているわけです。僕はそこにティツィアーノの寓話を見るのです」
「なんだかロブソンさんはこじつけているようですが、でも、言おうとされていることは分かってきましたよ」
「そうですか。これだけ話をしてきた甲斐がありますよ」
「ところで、ロブソンさんのエロチカ・オディッセイはクレタ島で始まりますよね。どうしてですか?これだけコリンスの事を語ったわけですから、ギリシャ本土で始まるのが自然だと思うのですけれど。。。」
「そうですよ。コリンスで始まっても別に問題はないんです。でもね、アフロディテはギリシャ本土で生まれたんじゃないんですよ」
「コリンスで生まれたのではないのですか?」
「違うんですよ。そのことについては次の機会に説明します」
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis4.html
きれいな写真がたくさん貼ってありますから、ぜひクリックして読んでみてください。
コリンスの美女 [西洋史・オリエント史]
コリンスの美女
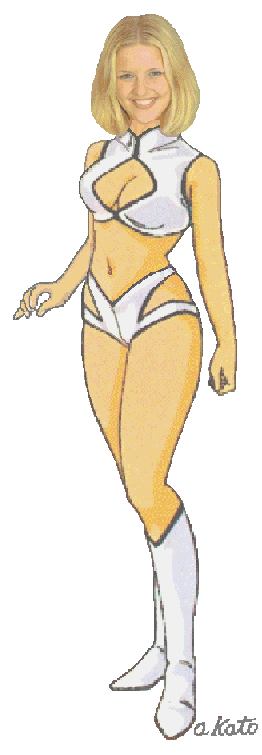
これからお話しする「ラピスラズリ と 美女アメニア」と言う物語は実は僕が英語で書いた “Erotica Odyssey”という歴史エロチカ大ロマンの第1章です。この物語は全部で21章からなっており、初版は1000ページを越す膨大なものになりました。現在の版は贅肉を削(そ)いでかなり身軽にしたものです。
次に示すようにBook1とBook2に分かれています。それぞれのリンクをクリックすると、簡単な紹介記事を読むことが出来ます。
「ロブソンさん、私、英語版を読ませてもらいましたよ」
「ジューンさん、読んでくれましたか。それでどうでした?」
「とにかく長いですねェ~。よくあれだけのものを書きましたね」
「なんだか、呆れたようなものの言い方をしますね?」
「別に呆れたわけじゃないですけれど、よく書く種がつきませんでしたね」
「古典の『オディセイア』も随分と長いですよ」
「長いですけど、ずっと昔に書かれたものでしょう?紀元前7世紀ごろに書かれた、というようなことを読んだことがありますよ。他に何もすることがなく時間をもてあましていた人が書きとめたのでしょう?ロブソンさんにはお仕事があるでしょう」
「もちろんですよ。だから、暇を見ては書き溜めたんですよ。それでどう思いました?」
「やっぱりエロっぽいところがたくさんありますねェ~」
「ジューンさんはエロいのは嫌いですか?」
「嫌いではありません。むしろ興味がありますよ。でも、このサイトはアダルトではありませんから、英語版を日本語に訳してここに載せたら削除されるのではないですか?」
「だから、トーンダウンして書きますよ」
「そんなことしたら、面白みがなくなってしまうのでは?」
「大丈夫ですよ。削除されない程度にエロい事も盛り込みますから。。。」
「どのようにして?」
「だから、セックスシーンをリアルに書かなければいいんですよ。詩的にぼやかして書きますよ」
「でも、ロブソンさん、小説の中のイラストなんか、かなり写実的ですよ。欧米ではまず問題にならないですけれど、日本では問題にする人も居るのではないですか?」
「そうですよ。僕もその事を考えました。でもね、僕にしてみれば、その程度のイラストなど、美術教室のデッサンと全く変わりがありませんよ」
「絵画の素養のある人なら、デッサンと言うことで目くじら立てる人は居ないと思いますよ。でも、デッサンなど全く無関心なオバタリアンがこのイラストを見たらきっとポルノだと言って騒ぎ立てますよ」
「そう思いますか?」
「たぶんね 。。。」
「僕はね、削除されるのは馴れっこになっていますから、もしこの程度でポルノだと判断するのなら、削除されることも覚悟していますよ」
「英語版のほうはアダルトサイトにアップしたんでしょう?」
「そうなんですよ。しかし、もともとはアメリカの一般のプロバイダーのサーバーにアップしたんですよ。1年間ぐらいなんともなかったんですよ。でも、他のページの写真がポルノだと判断されたようで、アメリカのプロバイダーが英語版のErotica Odysseyと一緒に削除してしまったんですよ」
「では、Erotica Odyssey自体は問題がなかったわけですね?」
「そういうことですよ」
「じゃあ、どうしてアダルトサイトにアップしたんですか?」
「実は、一般サイトにも載せているんですよ。でもね、またものの分からない人が告げ口でもして、削除されると面倒なので、手間を省くためにアダルトサイトにも載せたわけですよ。そうすれば、削除されてもすぐに続きが読めるでしょう」
「随分手回しがいいですねェ。それでもし、このサイトの日本語版エロチカ大ロマンが削除されたらアダルトサイトに載せるわけですか?」
「そうするしかないでしょうね。」
「ロブソンさん、ところでどうしてエロチカ・オディッセイを書く気になったのですか?」
「僕は欧米で生活するようになってから、『オディッセイ』と言う言葉をよく耳にしたんですよ。もちろん日本に居たときにも知っていました。でも、たくさんの英語の単語の中の一つぐらいにしか思いませんでした」
「でも、ロブソンさんにとって特別な意味があったと言うわけですか?」
「僕にとってと言うより、欧米人にとって『オディッセイ』というのは教養のうちでしょう?ジューンさんだって知っているでしょう?」
「まあ、そうですね。『オディッセイ』を知らない人はまず居ないでしょうね」
「僕は知らなかったんですよ。言葉は知っていましたが、内容は分からなかった」
「それで、『オディッセイ』を読んだわけですか?」
「いや、読まなかった。荒筋だけを読んで止めにしてしまった。あんな長いの読む気になれないよ。しかも、英語で読むのはしんどいよ」
「そのように言うロブソンさんが、どうしてまた、きりもなく長いエロチカ・オディッセイを書き始めたのですか?」
「僕はね、『オディッセイ』を調べているうちに、この大叙事詩が欧米人の原点のような気がしてきたんですよ。つまり、現代欧米文明は古代ギリシャ文明、古代ローマ文明から営々と続いていると考えている人が多いんだよね。だから、イギリスなどでは、古代ギリシャ古代ローマの古典をとにかく飽きるほど勉強させられる。そんな印象を持ったんですよ」
「私は飽きるほどは勉強しませんでしたけれど。。。」
「中にはそう言う人も居るでしょう。とにかくね、日本で言うなら、『オディッセイ』というのは古事記や日本書紀、あるいは源氏物語に匹敵するようなものですよ。もし、日本人でありながら、源氏物語を知らないとしたら、かなりその人の教養を疑われてしまう。僕は、ちょうどそのような思いに駆られたんですよ」
「つまり、『オディッセイ』を知らないと欧米でバカにされると思ったわけですね?」
「手っ取り早く言えばそう言うことですよ。ところで僕はね、カナダでもアメリカでも、初め無神論者だと言っていたんですよ。でも、今から思うとかなり恥ずかしい気がしてきますね」
「そうですか?」
 「そうですかって、ジューンさんだって、いま、僕を見下げたような目つきをしたじゃないか!」
「そうですかって、ジューンさんだって、いま、僕を見下げたような目つきをしたじゃないか!」
「しませんよ」
「しましたよ、僕を哀れむような、可哀想だと思うような、そんな目つきでしたよ。。。」
「しません。。。。ロブソンさん、被害妄想ですよ」
「まあ、いいよ。。。とにかく、日本で言うなら、さしずめ『僕は字が読めません』と告白するようなものなんですよね。つまりね、何がいいたいか?それはね、欧米で『オディッセイ』を知りませんと言うことは、神を信じていません、と言うに等しいことなんですよね。日本でなら、『字が読めません書けません』と言うに等しいことなんですよ。僕は、そのことに気付いたんですよ」
「それで、エロチカ・オディッセイを書く気になったと言うのですか?」
「長い話を短くして言えばそういう事なんですよ。でも、それでは、あまりにもはしょった言い方だから、もう少し付け足すなら、『オディッセイ』を面白く勉強しようと思ったわけですよ」
「面白くって、どういう風にですか?」
「視点をエロい所に持ってゆき、そこから『オディッセイ』を眺めてみよう思ったわけですよ」
「ロブソンさんは面白い事を言いますねェ」
「エロっぽいところから『オディッセイ』を調べるのなら面白いと思ったわけですよ。そうでない限り、あんな長ったらしい叙事詩を百科事典を調べたり、英英辞典を調べたりして読むのは、僕にとってとてもしんどいことですよ」
「それで、面白かったですか?」
「面白かった。実に楽しかった。僕は、歴史を調べることの面白さを初めて知りましたよ」
「それ程エロい事にたくさん出くわしたのですか?」
「そうですよ。たくさん出くわしました」
「そう言う事をロブソンさんのエロチカ・オディッセイの中に書いたわけですか?」
「そうですよ」
「しかし、私は『オディッセイ』の中にエロいものがたくさんあるとは思いませんけれど。。。」
「表面的に読めば、エロい所などほとんどありませんよ。だから、そう言う風に読んでは、つまらないわけですよ」
「エロい事をでっち上げると言うことですか?」
「いや、でっち上げると言うことじゃないんですよ。勝手に想像して何も関係のない事を書いたわけじゃないんですよ」
「どういう風にエロい事を書いたわけですか?」
「つまり、脇道にそれたり回り道をしたと言うことですよ。例えばね、女性の職業で一番古いものは何か?ジューンさん知っているでしょう?」
「ええ、プロスティチュートでしょう?」
「そうですよ。でも、日本語で娼婦と書いたら、これはもう身も蓋もない話になってしまう」
「プロスティチュートは日本語で娼婦とか売春婦と言う意味でしょう?」
「確かにそういう風に訳されることが多い。でもね、ギリシャ古典のオディッセイアが初めて本として書かれた頃にはプロスティチュートに当たる古代ギリシャ語は (実はたくさんあるのだけれど) 今の日本語で言うなら巫女さんに近かった。つまり神にかしずく女性だった」
「男なら、牧師さんや神父さんと言うところですか?」
「そういうことですよ。例えば、古代ギリシャにコリンスと言う町がある。今でもありますよ。現地ではコリントスと呼ばれているようですね」
「また、どうしてギリシャのコリントスが出てくるのですか?」
「古代ローマに地理学者として有名なはストラボン(Strabo)と言う人がいたんですよ。このおっさんが当時のコリンスについて書いているんです」
「当時っていつ頃のことですか?」
「このおっさんは紀元前64年頃生まれて、紀元後21年頃亡くなったことになっているよ」
「ということは、85歳で亡くなったと言うことですか?随分長生きしたんですねェ~」
「そうなんだよね。この人は、とにかく当時のローマ帝国全土の地理・歴史をまとめて『地理誌(Geography)』という本を著したんだよ。ただ無駄に長生きしたわけじゃない、このような貴重な地理誌を書き残しておいてくれたお陰で、現代の我々はいろいろな事を知ることが出来るわけですよ」
「それで、そのストラボンさんは一体どのような事を書いたのですか?」
「このコリンスの町は2つのことで有名だったらしい。一つは極めて裕福な町だったということ。もう一つはこの町の女たち」
「この町の女たちがプロスティチュートだったのですか?」
「もちろんすべてじゃない。でも、かなりの女性がプロスティチュートだったらしい。それがローマ帝国中に知れ渡っていたらしんだ」
「そうなんですか」
「ところで、アクロコリンス(Acrocorinth)と呼ばれる場所があるんですよ」
「それって、どういう意味なんですか?」
「アクロというのはギリシャ語でtopと言う意味ですよ。アテネのアクロポリス(acropolis)があるでしょう。あれと同じです。ポリスは都市ですからね。丘の上の町でしょう。アクロコリンスは、だから丘の上のコリンスとでも訳せばいいんでしょうね」
「栄えた都市だったのですか?」
「地図を見てもらうとよく分かると思うのだけれど、コリンスと言う町は栄えるような地理的な位置を占めているんですよ。現在は地図に書かれているように運河が掘られていて、コリンス湾とサロニカ湾が運河で結ばれているけれど、昔は文字通り船の通り道がこの場所にあって、コロで船を転がしてもう一方の湾へ導いたらしい」
「つまり、交通の要所を占めていたというわけですね」
「そういうわけですよ。スエズ運河のミ二チュア版ですよ。2001年の統計では、スエズ運河の通行料は世界の海運貿易の7%、年間にして19億ドルの外貨収入をあげている」
「と言うことは、単純に1ドル100円とすると日本円で1900億円と言うことですね?」
「あれ、ジューンさんはけっこう計算が速いね。カナダ人には計算が苦手な人が実に多いんだよ。。。」

「そのぐらいの計算なら私にでも出来ますよ」
「とにかく、この町はこの2つの港からの儲けを独り占めしていたわけですよ」
「でも、女性がどうしてそれ程有名になったのですか?」
「昔から港町にはその種の女性がたむろするものなんですよ。現在だって、世界の港町にはこの種の女性の溜まり場がありますよ。例えば、アムステルダムですよ」

「この上の写真はなんですか?」
「これは、あの有名な飾り窓の女たちがたむろする赤線地帯ですよ。つまりRed-light Districtです」
「あの~~~、ロブソンさんもこの飾り窓の女性たちと面識がおありになるのですか?」
「ジューンさん、そのように改まって質問されると答えにくいなああ~~~」
「答えたくないのですね?」
「なんだか、ジューンさんに警察で尋問されているような気分になりましたよ」
「いいんですよ、別に答えたくないのなら。。。」
「いや~~、そうやってすねられてしまうと、このあと話が続かなくなるから答えますよ。もちろん、一人や二人とは面識がありますよ。せっかくアムステルダムへ行ったのですからね、世界的に有名なあの飾り窓の女性と会わずに帰ってくると言うのはもったいないですよ」
「もったいないから、会って来たのですか?」
「ジューンさん、そうやって絡(から)まないでくださいよ。別に犯罪を犯してきたわけじゃないんですからね」
「確かに、あそこでは政府公認らしいですからね」
「ジューンさん、よく知ってますねェ~。へへへへ。。。。」
「笑いでごまかそうとするのですか?」
「いや別に、ごまかしているわけじゃないんですよ。。。。じゃあ、次の話題にいきましょうねェ」
(ジューンさん、なんとなくブス~~として機嫌を損ねています。)
「僕はね、ただ、港町にはその類の女性が居るものだと言う事を例えとして出したまでのことなんですよ。ここで、売春が良いとか悪いとか議論するつもりはないんですよ。ただ事実として、現在の世界的な港町の実情をここで説明したまでのことです。古代ギリシャの港町コリンスでも、このことは本質的に変わりがなかったんですね。そう言うわけでたくさんの女性たちが船乗りの相手になって、一儲けしようとこの街にやってきたわけですよ」
「。。。」
「どうですか?ジューンさん、理解していただけたでしょうか?」
「。。。」
「分かりましたか?」
「でも、その説明では、現在の状況をただ大昔に当てはめたようなものだから、どこにも新鮮な見方がありませんよね?」
「さすが、ジューンさん。目の付け所が違いますね。痛いところを突いてきますね。確かにその通りですよ。こういう説明では全く面白みがないですよ」
「ロブソンさん、じらさないで、その面白い説明とやらを聞かせてくださいよ」
「では、まずミロのヴィーナスから話し始めないといけません」
「ミロのヴィーナスですか?」
「その通り。。。」
「関係あるのですか?」
「大有りですよ!」
「どのように?」
「ミロのヴィーナスと言うのは大抵の人が知っていますよね。ルーブル美術館にある像はあまりにも有名になりました。ちょうどそのようにコリンスのヴィーナスは古代ギリシャ世界にはあまねく知れ渡っていたんですよ。ちょうどミロのヴィーナスのようにね」
「でも、ヴィーナスと言うのは古代ローマの愛の女神でしょう?」
「そうです。でも、もともとは古代ギリシャのアフロディテ(Aphrodite)を借りてきたものですよ。ローマ人は、ギリシア人のような独創的な文化を創り出すことができなかった。ギリシア文化・ヘレニズム文化の模倣におわってしまった。ただし古代ギリシャ文化を集大成し、後世に伝えたという点では功績を残しました」
「でも、ローマの水道だとか、コロシアムだとか、古代ローマ時代に作った道路網などはすごいじゃないですか」
「確かにそうです。僕も、古代ローマ人がギリシャ人の物真似に始終していたというつもりはありませんよ。法律や土木建築などの実用面には長所を発揮しました。でもね文学、哲学、歴史学や神に関わる分野ではギリシア・ヘレニズム文化の影響を強く受けました。そういうわけで、古代ローマのヴィーナスもね、アフロディテの影響を強く受けているわけです」
「でも、日本では圧倒的にアフロディテよりもヴィーナスのほうが有名ですね?」
「そうです。だから僕も、初めにヴィーナスを持ち出したんですよ。そのほうが分かりやすいですからね。初めにアフロディテなんて言っても、全く分からない人も居ると思いましたからね。でも、ヴィーナスと言えば、日本人のほとんどすべての人が知っていますよ。そう言う意味でも、古代ローマ人が古代ギリシャ文化を集大成し、後世に伝えたという点では功績を残したと思いますね。つまり、アフロディテをヴィーナスとしてね」
「それで、そのアフロディテが、どのように関わってくるのですか?」
「それは、また次の機会に説明します」
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis3.html
きれいな写真や地図がたくさん貼ってあります。
興味のある人はぜひ読んでみてください。
ラピスラズリと美女アメニア [西洋史・オリエント史]
ラピスラズリと美女アメニア
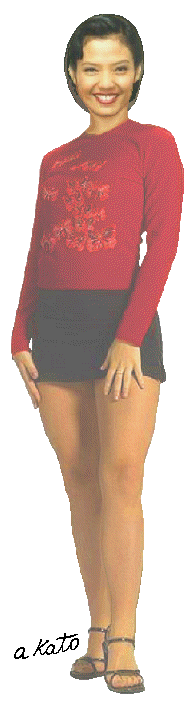
これからお話しする「ラピスラズリ と 美女アメニア」と言う物語は実は僕が英語で書いた“Erotica Odyssey”という歴史エロチカ大ロマンの第1章です。
この物語は全部で21章からなっており、初版は1000ページを越す膨大なものになりました。
現在の版は贅肉を削(そ)いでかなり身軽にしたものです。次に示すようにBook1とBook2に分かれています。
それぞれのリンクをクリックすると、簡単な紹介記事を読むことが出来ます。
まだ日本語に翻訳していません。つまり英語で考えて英語で書いたのです。
自分で書いたものでも日本語に訳すのってしんどいです。日本語の下書きというものを全く用意しませんでしたから。
僕はもう人生の半分以上を海外で暮らしています。でも、同時通訳的に訳すことは出来ません。
あれは、長く外国に住んだからといって、誰にでも身に付く能力ではないですね。少なくとも、僕には出来ません。
そう言うわけで訳すのは面倒なんですよね。だから、日本語は日本語で考えて書くし、英語は英語で考えて書きます。
どうして、僕が第1章を日本語で書こうと思いたったかというと、たまたまCOMMIT4Uというソーシャル・コミュニティでオーストラリアのブリスベンに住むアミサさんという女性とメールを交わすようになったんです。
彼女はデザインを勉強している日本人の大学生です。そのメールの中でラピスラズリが話題になったことがそもそも“ラピスラズリとラピスラズリ・ロード”を書くきっかけになったのです。
でも、そのページではこの第1章に触れることはほとんどありませんでした。
いわばこの第1章のバックグラウンドになる事を書いただけだったのです。
本当に面白いことが残されてしまったのです。そのようなわけで、このページを第2部として“ラピスラズリとラピスラズリ・ロード”の続きという形で書こうと思い立ったわけです。
ところで「袖擦れ合うも他生の縁」という古言がありますが、時々僕は不思議な縁を感じることがあります。
これまでの人生で、このような不思議な縁を感じたことがたびたびありましたから、今回のアミサさんに感じた縁がとりわけ不思議だというほどのものではないのですが、ユニークであることには変わりがありません。
では、何が一番ユニークかといえば、アミサ(Amisa)さんの、このハンドル名と僕の物語の中に出てくるヒロインの名前(Amenia)が良く似ているということなんですね。もちろん、アミサさんは僕の小説など読んでいないし、僕だってこれまでにアミサさんと会ったこともないのです。
Amisaは5文字。Ameniaは6文字です。アミサのSを除いてすべての文字がAmeniaに含まれているのです。
次にユニークなものは何か?
それは僕がたまたま書いた記事『なぜ厩戸王子なの?』の中で次のように「四騎獅子狩り文錦」を引用していたのです。

この夢殿に伝来された四騎獅子狩り文錦の図柄は、ササン朝ペルシャ(226~651)で大流行したデザインです。
シルクロードを経て中国に伝搬し、大和朝廷にも伝わりました。奈良時代の金属器や染織品の文様につかわれています。
これまで見てきたように、太子を取り巻く人間模様というのも、上に見る四騎獅子狩り文錦の図柄のように、そばによって、じっくり見ないと、何がなんだか分からないような、複雑怪奇な様相を呈しています。
この記事を僕のブログにも書いたのですが、それに対してアミサさんが次のようなコメントを書いてくれたのです。
name: ☆アミサ★
ところで獅子狩文錦のデザインって私好きです。
あの柄の袱紗持ってるんですよーすごく綺麗です☆
-----------------------------------------------
date: 2005/06/02 16:22:12
name: ロブソン
あの柄の袱紗持ってるんですか?
僕も是非みたいですねぇ~~。
すごく綺麗だったら、是非みたいですよ。
デジカメで撮ってアップしてくれると、
僕は随喜の涙を流して喜んでしまうかも知れませんよ。
(^Д^)ギャハハハハ。。。。
上の写真はかなり色がくすんでいるんですよね。残念です。惜しいです。
時間がたっているから仕方が無いですけどねぇ。
僕のイメージとしては、瑠璃色をふんだんに使った図柄がペルシャにふさわしいような気がしているんですよ。
そんな袱紗を夢想しています。。。。
アミサさんが付けてくれたコメントに返信を書いてから、僕はこの記事のことは忘れていました。
1週間ぐらいしてから、ブログのプロバイダーからメール着信の知らせを受け取りました。
誰かが僕にメールを書いたという知らせです。ボックスを開いてみるとアミサさんからでした。
ネーム ☆アミサ★
日付 2005/06/12 05:57
覚えていますでしょーか?アミサです!
今から私の獅子狩り文錦柄の袱紗の写真を
載せますv模様自体はあの四の獅子がいるあれよりも
シンプルで簡単なものですけど、おきにいりです☆
------------------------------------------------
件名 RE:こんにちは~
ネーム ロブソン
日付 2005/06/12 06:34
もちろん、よ~~~く覚えていますよ!
そうですか。。。獅子狩り文錦柄の袱紗の写真をアップしますか。。。
期待していますよ。
見させてもらいますね。
というわけで、アミサさんがアップロードした写真が次に示すものです。
彼女のサイトに直リンクして表示しました。

デザインを勉強しているアミサさんだからこそ、獅子狩り文錦に関心を寄せ、その図柄の袱紗を買ったのでしょう。
僕はなぜこの獅子狩り文錦に興味を持ったかというと、獅子狩り文錦が遠くペルシャからシルクロードを通って古都・飛鳥に伝わってきたというロマンです。

ラピスラズリも同様にシルクロードを反対方向に伝わってバダフシャンからメソポタミアに伝わったのです。
その当時は“シルク・ロード”ではなく、むしろ“ラピスラズリ・ロード”だったわけです。
紀元前2500年頃、チグリス・ユーフラテス河のデルタ地帯に存在したシュメール人の古代都市国家ウル(現在はイラク)では、このラピスラズリがネックレス用に加工されました。プアビ女王の墓からラピスラズリのネックレスが出土しています。
またラピスラズリはメソポタミアからカナンに伝わり、フェニキア人によってクレタ島にももたらされたのでした。
ここでは、同じようなネックレスがクレタ島の“パリジャンヌ”の胸元を飾ったことでしょう。
下の写真に見るとおり、今から4000年前のクレタ島の女性はクレタ文明を発掘した考古学者アーサー・エヴァンズがフラスコ画に描かれていた彼女たちを見て、思わず“可愛いパリジャンヌ”と叫んだというエピソードが伝わっているように、4000年前とは思えないほど現代的なセンスを持っています。
僕がクレタ文明にロマンを感じるのはそのようなことも手伝っています。

この3人のクレタ女性はお祭りでなにやら愉快に話しをしています。
当時上流社会で流行していた胸を見せる短い胴着(bolero)を身に着けています。
当時も細いウエストが好まれたそうです。
というわけで、“Erotica Odyssey”は、この“パリジャンヌ”の一人がヒロインとして登場します。彼女の名がアメニアです。
随分長い前置きになりましたが、このようなわけで、もう一度歴史エロチカ大ロマンを日本語で味わってみようと思い立って書き始めました。
そのきっかけを与えてくれたのがアミサさんだったというわけです。

ついでですから、ここでもう一つのユニークさを披露しましょう。それは、アミサさんが住んでいるBrisbaneのことです。
この町のことは実はジューンさんから聞いていました。彼女は小学生の頃、3年ほどこの町に住んでいたことがあるそうです。それで、僕にはこの町の名前の響きがなんとなく馴染みがあったわけです。
ブリスベンと言うのはクイーズランド(Queensland)の港町です。この名前はSouth Wales州のガバナーだった人の名前にちなんで付けられたようです。
僕の書いた小説の題名(Erotica Odyssey)からも分かるように、この話はOdysseusにまつわる話です。
Odysseusといえば、トロイ戦争とは切っても切れない関係がありますよね。そういうわけで、僕には古代オリエントの響きとして聞こえてくるのです。
僕がこの町の名前から夢想するのは、あの古代オリエントのトロイ戦争です。
なぜか?
Briseisという女性が居ました。この女性の名前がBrisbaneに似ているわけです。ブリーセイスと日本語では呼ばれているようですね。
この戦争で捕虜になった女性です。アキレス(Achilles)が貰い受けた女性なんですよね。クリセイス(Chryseis)との交換でアガメムノン(Agamemnon)がまず獲得し、アキレスは親友パトロクラス(Patroclus)の死で戦いを終らせた後、譲り受けたようです。
Baneというのは、致命傷とか破滅とか死と訳されます。つまりトロイ戦争にまつわるたくさんの英雄の死を連想させます。
僕にとって、このBrisbaneというのはトロイ戦争でブリーセイスがこの戦争で体験した“死の悲しみ”なんですよね。
つまり、Briseis の Bane。 それで、Brisbane と言うのが僕流のBrisbaneという単語の起源です。
もちろん、このようなことはどの歴史書にも書いてありません。古代オリエント史にかぶれている歴史馬鹿の僕が考えたことですから。。。。

この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/lapis2.html
上のリンクをクリックするとオリジナルのページを読むことができます。
きれいな写真がたくさん使ってあります。面白いリンクも貼ってありますよ。
ぜひ飛んでみてくださいね。
古代紫 [西洋史・オリエント史]
古代紫
Tyrian purple
岩波の理化学辞典には、 Tyrian Purple は「古代紫」の名称で取り上げられています。
この項には次のように書かれています。
 【古代紫】
【古代紫】地中海産の貝
purpura、Murex、Thais 属の
鰓下腺(サイカセン)から分泌される黄色液で、
主な色素成分は、
6.6’-ジブロモインディゴ C16 H8 O2 N2 Br2。
これで繊維を染めて空気にさらすと、
紫に近い深紅色に変わる。
ギリシャ・ローマ時代における
貴重な紫色素で高価であった。
ところで僕が日常使っている三省堂の国語辞典には次のように出ています。

【古代紫】
多少灰色がかった紫。
江戸紫よりも黒味を帯びている。
僕の頭の中では「古代紫」というのはTyrian purpleのことなんですが、国語辞典の定義にある「古代紫」とは全く違っているようですよね。
Tyrian purpleと言う色は理化学辞典で説明されているように「紫に近い深紅色」なんですね。
国語辞典で定義されているような「多少灰色がかった紫。江戸紫よりも黒味を帯びている」色ではありません。

では、Tyrian purpleとはどのような色をしているのかと調べたら、右の絵に書かれている人物が身にまとっている帽子と上着の色がその色なのです。古代紫とも江戸紫とも違い、かなり赤みを帯びています。
古代紫には人によってかなりの受け止め方に違いがあるようです。
むしろ「貝紫」と言ったほうが的確かもしれません。
貝紫とは磯に住むイボニシやレイシ、アカニシ、センジュガイといったアクキガイ(悪鬼貝)科の巻貝(murex)から取れる染料のことです。
この貝が持つ鰓下腺(通称パープル腺)から分泌される乳白色~淡黄色の液は、太陽の光にあたると酸化されて紫色に変化する性質があります。
この分泌液は6.6ジブロムインディゴと呼ばれる色素の1種が還元された状態で貯蔵されているもので、神経を麻痺させる作用があるため、他の魚貝類を攻撃する武器になると共に産卵期には卵殻の中に注入して、卵が他の生物に食われないようにする役目も果たしています。
アクキガイ科の貝の中には食用になるものもあり、大昔から海辺の人々によって採捕されて来ましたが、殻を割って料理する際、内臓が手や衣服に付着して紫色に変化するのを見て、染色に利用することを思いついたのでしょう。
この貝から取れる染料に基づいた染色法は地中海沿岸の古代フェニキアで行われ、それがギリシャ・ローマ時代に受け継がれていったものです。
これで染めた衣服を着られるのは王候貴族に限られていました。
歴史書によると、貝紫は1gの染料を取るために二千個もの貝を必要としたとあります。
ちょっとオーバーじゃないかと思うのですが、とにかく希少価値であったことには違いないようです。
そのようなわけで極めて高価な色として珍重されました。
ちなみに1万個の貝から1gと書いてあるウェブページがありました。
二千個でもオーバーだと思ったのですが、1万個はさらにオーバーじゃないかと思いますね。
でも、それ程わずかしか取れないということは、このような記述から確かなようです。
Tyrian purpleとは“Tyre(ティルス)で貝から取れた紫”ということです。
このTyreというのは古代のフェニキアの都市です。
現在は es-Sur と呼ばれるレバノンにある小さな村です。

このフェニキア人は、紀元前15世紀頃から紀元前8世紀頃にティルス、シドン、ビュブロスなどの都市国家を形成して海上交易に乗り出し、のちにはカルタゴなどの海外植民地を建設して地中海沿岸の広い地域に渡って活躍しました。
フェニキア人は系統的には様々な民族と混ざって形成された民族です。
彼らはアフロ・アジア語族セム語派に属するフェニキア語を話し、言語的に見ればカナン人の系統に属する民族です。
彼らが自分たちの言葉を書き表すために発明したフェニキア文字は、ギリシャ文字・アラム文字・アラビア文字・ヘブライ文字など、ヨーロッパ・西アジアの多くの言語で用いられる文字の起源になりました。
もちろん、英語のアルファベットもこの系統です。
貝紫はこの古代フェニキア人が最初に染料として用いたことになっていますが、歴史研究者の中には、その起源はもっと古くクレタ文明(ミノス文明とも呼ばれます)でも使われていたとする人たちも居ます。
レウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島が、上の地図で示したようにクレタ本島の南東にありますが、この小島には初期のクレタ文明(紀元前3000-2200年)の頃に貝紫が取引されていたという記録が残っています。紀元4世紀までは人が住んでいましたが、現在は無人島です。
個人的には僕は貝紫の起源はクレタ文明だと思いますね。
なぜなら、この文明は男も女も身だしなみに、ことのほか気を使ったのです。
考古学者のアーサー・エヴァンズはクノッソスで発掘調査した時に次に示すフレスコ画を見つけました。
これを見た彼は“可愛いパリジェンヌ”と言って驚いたという話が伝わっていますが、確かにナウい感じがしませんか?

“Ladies in Blue” fresco from Knossos, 16th century BC.
この3人のクレタ女性はお祭りでなにやら愉快に話しをしています。
当時上流社会で流行していた胸を見せる短い胴着(bolero)を身に着けています。
当時も細いウエストが好まれたそうです。この胴着の肩当を見てください。
これは貝紫で染めてあると思いませんか?ちょっと色が茶色っぽく変色していますが、これが描かれた時にはもっと赤みを帯びていたのではないでしょうか?

ヘアスタイルといい現代風なスカートといいセックスアピールする胴着といい、もしクレタ島の“パリジェンヌ”と19世紀のパリジェンヌが次に示すように町の通りを歩いていたら、19世紀の女性はダサいと思われてしまうのではないでしょうか?
我々の眼にはフープ・スカートは明らかに時代遅れと映りますよね。


“どちらの女性と喫茶店に入って話がしたいですか?”と問われれば、僕はおそらくクレタ島の女性に声をかけるでしょう。
バルキーなスカートをはいた女性は、やはりダサいですよ。クレタ島の女性の方がモダンな感じがしませんか?19世紀の女性のように、こんな幅広のスカートをはいて喫茶店に入ったら、周りの人が迷惑するでしょうね。(笑)
19世紀の女性と比較するのでは、時代が違いすぎるので、同じ時代のエジプトの女性と比べてみたいと思います。
次の絵の中の女性たちは今から3500年から3000年前の服装をしています。
上のクレタ島の“パリジェンヌ”とほぼ同じ時代です。

一目見ただけでも、エジプトの女性の方がシンプルですよね。というか、言葉は悪いですが“土人スタイル”ですよね。
パリジェンヌよりも原始的な感じがします。我々の眼には、どう見てもクレタ島の女性の方が現代的な印象を与えます。
そう思いませんか?
いづれにしても、クレタ文明では5000年も前から貝紫が使われていたんです。
その貝紫を抽出していたのがレウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島だったわけです。
恐らく、この島からフェニキア商人によって抽出技術がティルスに伝わったのでしょう。
ところで、日本にも古代地中海から伝わったものがあります。
それは古代に中国の絹織物がヨーロッパへと運ばれてた道、シルクロードを通じて運ばれてきました。
奈良の正倉院に収められている楽器を彩る紫の色は古代の日本でも最も高貴な色とされていました。
でも、それは日本独自の考えで紫を選んだわけではありません。
紫を最高級の色とする考えは、地中海でとれる貝紫という染料から始まっているのです。
ところが、貝で染める紫の染料は弥生時代の日本でも使われていたのです。
佐賀県の吉野ヶ里遺跡は弥生時代先期から中期(B.C.3世紀~A.D.1世紀)の古代人の遺跡です。
吉野ヶ里遺跡では弥生中期頃の甕棺墓が多数発掘されています。
その甕棺に葬られていた人骨に付着している織物を分析した結果が報告されています。
その報告によると、布は絹織物で蚕の種類は違っているようですが、日本国内の蚕から得られたものです。またその絹織物の一部に貝紫で染められたと見られるものが残されているのです。
当時、絹織物を身につけることのできた人物は、集落の中でも高い身分の人であったと考えられます。
貝紫染めの織物を身につけることのできた人物は極く限られた人であったでしょう。
ここで問題です。貝紫染めは地中海沿岸だけで行われていたと考えている人が多いようです。
吉野ヶ里遺跡で国産の絹が貝紫染めされていたということは意外な感じがします。
日本でも弥生時代にすでに貝紫染めが行われていたという事実をどのように解釈すればよいのか?
極めて難しい染色がなぜ地中海と、遠く離れた有明海で行われていたのか?
現在のように通信手段の発達した世界ならば、情報はあっと云う間に地球の端から端まで伝えられます。
しかし、今から2000年以上も昔に地球の表と裏で、なぜ同じような染色が行われていたのか?
ところで、この問題に答える前に貝紫染めの染色法をさらに詳しく見てみたいと思います。
貝紫染めの染色法には、直接染色法と還元染色法の2つの方法があります。
ここでは直接染色法を取り上げてみたいと思います。
ビーカー染めの場合だと、染料をそのまま水に溶かすか水に溶かした溶液を使います。
貝紫染めでは、まずビーカー染めの染料となるものを貝から取り出す作業があります。
色素となるのは貝の組織の一部鰓下腺から分泌される液です。鰓下腺は長さ5㎜程度の組織です。
貝を金床の上に置いて金づちで貝を割ります。貝を割って貝の組織をピンセットで取り出し、鰓下腺を探し取り出します。金づちで打つ位置が悪いと鰓下腺をつぶしてしまいます。
慣れて割にうまく取り出せるまでにかなりの時間がかかります。
馴れないと、貝を無駄にすることになります。上で1gの染料を作り出すのに、ある文献では2000個と書いてあり、別の文献では1万個と書いてあるのは、恐らくこの熟練の度合いに関係してくるのだと思います。
黄緑色をした鰓下腺をピンセットで組織から分離して、金網の目をくぐらせて手早くすりつぶします。
それに貝の分泌液や水を加えてペースト状に伸ばします。この液が目的の色素を含む液です。
この時の色は黄色から黄緑色でまだ完全な色素ではなく、色素前駆体と呼ばれるものです。
この液体を布か糸に浸して染色するのですが、この液体は作業を手早くしないと、空気中で酸化して良い色になりません。つまり、ここでも熟練が要求されます。
もう1つの問題は臭いです。鰓下腺をすりつぶして行くと強烈な臭いを発します。
染色のためには臭いも我慢しなければなりません。発色は日光に当てて行います。
発色は色相が、黄味―緑味―青味―紫(赤紫)へと段階的に変化して行きます。
発色が進んで行くにしたがって悪臭が徐々に消えて行きます。
ここで、手際が悪かったりペースト状に延ばすやり方がまずかったりすると、発色が不均一で緑のまま残った個所が出来たり、完全な赤紫にならない個所ができたりします。
ここでも熟練が要求されます。つまり、この染色法では工芸的な染色はできても、工場規模での大量生産は到底できません。要するに染料そのものが希少価値な上に、染色法がきわめて難しいわけです。
このように手の込んだ、しかも熟練を要する染色法が、地球の裏と表で偶然に発見されると言うことは考えにくいのです。もし“Tyrian purple”と言う流行がなかったら、悪臭を我慢し、面倒で手数のかかる貝紫を採る理由がどこにもありません。もっと簡単な方法で作れる染料で代用することができます。
でも、代用することが出来なかった。なぜなら、貝紫は、その染料が希少価値であるがゆえに“Royal Purple”と呼ばれていたからです。この貝紫で染めた衣服を身に着けることがステータスシンボルだったわけです。
だから、何が何でも貝紫でなければならなかった。
しかし、地中海と有明海の距離をどのように説明すればよいのか?あまりにも隔たりすぎていますよね。
でも、なにも“Tyrian purple”がTyreから伝わって来ると考える必要はありません。
紀元前3世紀までの間に、すぐお隣の朝鮮半島までその“流行”は何百年と言う年月を通して伝わっていたのです。

『なぜ厩戸王子なの?』と題する記事で紺瑠璃杯が遠くペルシャから伝わってきた様子を僕は説明しましたが、ちょうどそれと同じようにしてシルクロードを通して地中海から有明海に伝わってきたのです。そのように考えれば、地中海と有明海の隔たりは説明がつきます。
飛行機もない電話もない、ましてやネットもなかった時代ですが、人間はいつの時代でも情報を交換していたのです。
ただ、現在なら30分もすれば情報が世界を駆け巡りますが、昔はそれが何百年もかかる場合があったというだけの違いです。
この記事は次のページをコピーして編集したものです。
http://www.geocities.jp/barclay705/crete/purple.html



